講座302 誰が国語力を殺すのか?

「一般の方が見ている世界」と「学校の先生が見ている世界」とでは、
こんなに違うのかあー!
という衝撃的なことがあったので、今回はそのことを書きます。
2.ナニが問題なの?
3.国語の授業の基本
4.学校世界の病理
1.ルポ「ごんぎつね」
新見南吉の「ごんぎつね」という物語が4年生の国語の教科書に出ています。
いたずら好きの小ぎつねのごんは、兵十(ひょうじゅう)が捕ったウナギを軽い気持ちで逃がします。
それを後悔したごんは贈り物を兵十に届けるようになります。
しかし、忍び込んだ気配に気づいた兵十は鉄砲でごんを撃ってしまう。
というお話です。
教科書に次の場面があります。
よそいきの着物を着て、腰に手ぬぐいを下げたりした女たちが、表のかまどで火をたいています。
大きななべの中では、何かぐずぐずにえていました。
「ああ、そう式だ。」と、ごんは思いました。
「兵十の家のだれが死んだんだろう。」
兵十のお母さんが亡くなった時の場面です。
東京都内のある公立小学校で、この場面を扱った授業が行われました。
授業では教師が子どもたちを班に分けて「鍋で何を煮ているのか」などを話し合わせていました。
その授業を見ていたルポライターの石井光太さんが次のように報告しています。
生徒の間から耳を疑うような発言が飛び交いだした。『ルポ誰が国語力を殺すのか』(文藝春秋)
こんな発言です。
「この話の場面は、死んだお母さんをお鍋に入れて消毒しているところだと思います」
「もう死んでいるお母さんを消毒しても意味がないです」
「お湯で溶かして骨にしてから、お墓に埋めなければならなかったんだと思います」
「うちの班も同じです。死体をそのままにしたらばい菌とかすごいから」
石井さんは子どもたちのこうした発言に驚いたのでしょう。
次のように書いています。
常識的に読めば、参列者にふるまう食事を用意している場面だと想像できるはずだ。
ところが子どもたちは「死体」を煮ていると考えた。
石井さんはそのことに驚いたわけです。
どうですか?
みなさんも驚きましたか?
これは問題だ!と思いましたか?
どうして子どもたちはこのような発言をしてしまったのでしょう?
国語力が低下しているからだと思いますか?
ゲームのやり過ぎ?
石井さんは終章で次のように書かれています。
国語力を取材してきた私としては、もうこれ以上、子供たちが直面している国語力の問題から目をそらし続けるべきではないという思いを強くしている。
石井さんの強い危機感が表れている一文です。
私にもその「思い」はわかります。
でも、教師を経験してきた私としては、「問題」は別な所にあると考えます。
もっと言えば、子どもたちが鍋で死体を煮ているのではないかと発言しても、まったく驚かないわけです。
みなさんはどっちですか?
❞死体発言❞に驚きますか?驚きませんか?
そこが「一般の方が見ている世界」と「学校の先生が見ている世界」の違うところだと思うのです。

2.ナニが問題なの?
先日、私のYouTubeチャンネルでこの問題を取り上げてみました。
収録は、福井の吉田高志氏と東京の村野聡氏と私の三人で行いました。
三人とも30年以上の教職経験があります。
公開はしていませんが収録は吉田氏の次の言葉から始まりました。
これ、ナニが問題なの? 意味わからない。
❞死体発言❞に全然驚いていないわけです。
ここです。
これが「一般の方が見ている世界」と「学校の先生が見ている世界」との大きな違いです。
※ここでは違いを分かりやすくするために私たちのことを「学校の先生」とか「教師」と表現させていただきます。
「学校の先生」は驚かないわけです。
子どもたちの❞死体発言❞を問題だとは思わないのです。
村野氏も私も同じです。
「学校の先生」は「一般の方」とは違うところを見てしまうのです。
どこを見てしまうのか?
これは、発問が悪い。
発問を検討しちゃうんです。
教師のクセですね。
発問(はつもん)というのは、子どもたちに考えさせる時に使う教師の言葉です。
この場合は、教師が子どもたちを班に分けて「鍋で何を煮ているのか」などを話し合わせていました。
ですから、「鍋で何を煮ているのか」が発問になります。
「鍋で何を煮ているのか」を聞いてしまった。
ここが問題なのです。
これ、聞いちゃダメなんです。
教師の世界ではダメな発問なのです。
どうしてダメなのか分かりますか?
何を煮ているかなんて教科書の文章には書かれていないのです。
大きななべの中では、何かぐずぐずにえていました。
としか書かれていないわけです。
芋を煮ていたかもしれないし、雑炊を作っていたかもしれません。
文章に書かれていないわけですから想像するしかありません。
言ってしまえば自由です。
答えは無限です。
でも、授業者は子どもたちの考えを「一つの枠」にはめたかったのでしょう。
参列者にふるまう食事を作っていた(煮ていた)というような答えを期待していたのではないでしょうか。
でも、それは論理的に(国語力として)破綻しています。
何を煮ていたかなんて教科書の文章には書かれていません。
検討できる言葉や文章も書かれていません。
これは、発問が悪い。
というのが私たちの三人の見解です。

3.国語の授業の基本
どうですか?
ここまでを読んで納得できましたか?
きっとこれでもまだ納得されなかった方がいるんじゃないでしょうか。
もしそうだとしたら、それほど「一般の方が見ている世界」と「学校の先生が見ている世界」は違うということです。
常識的に読めば、参列者にふるまう食事を用意している場面だと想像できるはずだ。
私たち教師はそう思いません。
参列者にふるまう食事を用意している場面だと想像できない子どもがいるはずだ。
そう思います。
ですからここは、教えます。
「昔のお葬式というのは、たくさんの人が亡くなった人のおうちにやって来て、みんなで協力して準備をしたんです。だから、協力して下さった方々に食事を用意していました。ここは、女の人たちがその食事を用意している場面なんです」
そんな風に教えます。
時代背景が違いますから、想像できない子が多いはずなのです。
YouTube動画の中で吉田氏は自分が子どもの頃に経験したお葬式の話をされています。
裃(かみしも)を付けて列になって歩く場面まで覚えていたんです。
これは子どもたちに語ってあげたいですよね。
先生の実体験ですから。
また、村野氏は経験を補ってあげることの大切さを指摘されました。
写真や動画などで昔のお葬式の場面を提示するという方法も可能ですよね。
授業の名人と言われる教師の実践には、教室に実物を持ち込んで文章を検討させるという方法もあります。
方法は違いますが共通しているのは「ここは教える」ということです。
そして、大事なところ(文章をもとに読み取らせる場面)でこそ「教えない」のです。
それが国語の授業の基本です。
【国語の授業の基本】言葉にこだわる。文章を検討させる。
念のために確認しますと、文部科学省は国語という教科の目標を次のように示しています。
言葉による見方・考え方を働かせ,言語活動を通して,国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力を育成することを目指す。
何を煮ていたかが書かれていない文章において、「何を煮ていたのか」と聞くのは国語の授業として「発問が悪い」ということなのです。

4.学校世界の病理
どうでしょう?
これで私たち教師の見ている世界が少しは見えてきたでしょうか?
最後に、この世界の病理とも言うべき裏の事情について触れて終わります。
この❞死体発言❞が出た小学校の校長先生は石井さんに対して次のように説明されています。
今日のケースは少々極端でしたが、最近は多かれ少なかれあのような意見が出るのは普通です。教員もそれをわかっているので、先ほどの授業でも班になって話し合わせたのでしょう。それでもああいう回答になってしまったようですが…。残念ながら、似たようなことは、私も他の学校でしばしば経験してきました。(前掲著)
ここは「それでも」ではないのです。
「それだから」ああいう回答が出てきたのです。
そして、病理というのは「話し合わせたこと」です。
話し合いは大事、話し合わせるのが授業、というような呪縛が学校教育の一部に存在しているのです。
グループにして話し合わせていれば、なんとなく授業をしているように見えてしまうのです。
そういう授業は、参観日や公開授業などで時折見かけます。
見ている方も、それで授業っぽく見えてしまうのです。
私たちのように「発問が悪い」なんて考えないわけです。
❞死体発言❞を例にするなら、子どもたちに経験がないにも関わらず話し合わせているわけです。
読解の責任を子どもたちに投げてしまったようなものです。
こういうことが「しばしば」あるわけです。
最後に、三人を代表して私が主張させていただきます。
長く教師をしてきた者として、もうこれ以上、子供たちが直面している「教師力」の問題から目をそらし続けるべきではないという思いを強くしている。
収録した動画の中で村野氏は言いました。
先生がそういう風に聞くから、子どもたちは一所懸命考えて発表しているにもかかわらず、子どもたちの解釈に問題があるような論調になっている。(要約水野)
さらに、吉田氏はこう言いました。
そう聞かれたので、もしかしたらお母さんの死体を煮ているのかな?と考えたけど、そんなことは発言できないな…と思って口をつぐんだ子もいると思う。(要約水野)
どうですか?
これが教師の視点です。
「一般の方が見ている世界」と「学校の先生が見ている世界」との違いを理解していただけましたでしょうか。

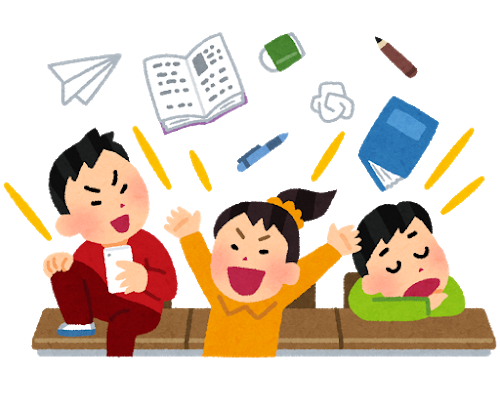



とても納得しました。国語力を低下させているのは教師でした。書いていないことを想像で発表させる発問。気持ち悪いくらい気持ちを問う発問。結果、班で話し合わせても深まらず迷走してしまう。元教師として、恥ずかしいやら、いや自分はそれをしなかったぞという言い訳も・・・(←しても意味なし?)
大北先生、読み取っていただきありがとうございます。教師力の育成と家庭教育への質的支援が急務だと思っております。
教師になって初めて聞いた発問で、驚きです。このような発問を思いついたこともないので、とても衝撃を受けました。研究授業だから発覚しましたが、普段からこんな変な発問をしているのかと思うと、子供の国語力が低下しているのに納得しました。学校で問題提起していかないといけないなと思いました。ありがとうございます!
コメントありがとうございます。
教師の世界は「二つに分裂」していると、かつて向山洋一氏は主張されました。
1「全員を跳ばせられる教師」と「クラスに何人も跳べない子がいる教師」
2「お金を出して本を購入するなどして学んでいる教師」と「教育書も教育雑誌も読まない教師」
3「できない子を何とかしてできるようにしたいという教師」と「できない子がいても何も感じない教師」
「このような発問を思いついたこともない」という田中先生は間違いなく後者ですね!