講座140 覚えてますか?「子育て四訓」
親子の関係性をシンプルに示した名言です。
秩父神社の薗田稔氏が唱えた『親の心得』が原典だと言われています。

今回は「子育て四訓」の解説です。
2.思春期の親子関係
3.思春期「5つの特徴」
4.心でつながるには?

1.乳児期~少年期の親子関係

乳児はしっかり肌を離すな。
これは乳児期の親子関係を表す一文です。
「スキンシップ=愛着形成」ですね。
幼児は肌を離せ、手を離すな。
幼児期の親子関係です。
歩けるようになってますから「下におろす」段階ですね。
でもまだ愛情が必要ですから「付かず、離れず」ということですね。
少年期に入って、手が離れます。
学校に行って友だちと遊ぶようになり、生活範囲が広がります。
でもまだ子どもですからね。手から離れても、親は、
「何をしているのか」を把握していなければなりません。
それが、
少年は手を離せ、目を離すな。
です。

2.思春期の親子関係

ということで、思春期(青年期)はどうなりますか?
ここが今回の本題です。

3.思春期「5つの特徴」
講座135で、思春期「5つの特徴」を解説しました。覚えてますか?
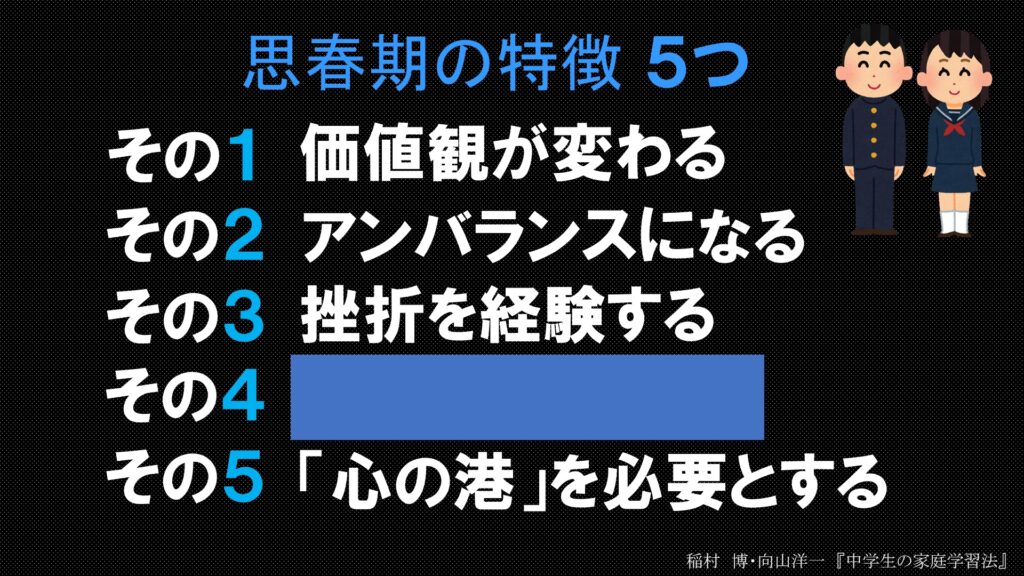
その4つ目は何だったでしょう?
こんな感じです。
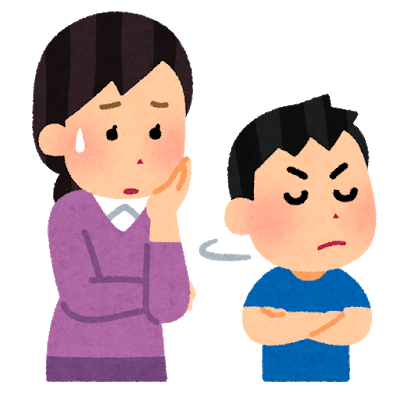
その4は、「素直になれない」です。
反抗期と言ってもいいでしょう。
親に見られただけでもムカッとしたりします。
口に出したら余計です。
そんな時期ですから、「子育て四訓」の四つ目はこうなります。

青年は目を離せ、心を離すな。
少し寂しいのですが、そういう時期を通るのはダメなことではありません。

「そういう時期なんだ」ということですね。

4.心でつながるには?
じゃあ、目を離して心を離さないって、どうすればいいのでしょう?
これは私の考えなのですが、
➀余計なことをしない。
②淡々と当たり前のことをし続ける。
それがいいように思います。
たとえば「食事を作る」って当たり前のことですよね。
思春期でも腹がへります。
一緒のテーブルで食べる機会はなくなるかも知れませんが「食べること」は必要でしょう。
思春期にはこうした「当たり前のこと」が愛情になります。
「食事を作ってあげる」「洗濯をしてあげる」「送り迎えをしてあげる」…。
直接的なコミュニケーションは少なるかもしれませんが、
「何かひとつ」のことでつながっていれば、それが「心を離すな」になる
と思うのです。
私の子育て講座ではいつも東京ガスのこのCMを紹介させていただいてます。
ご存知ない方はぜひご覧ください。






1件の返信
[…] 講座140 覚えてますか?「子育て四訓」 […]