講座72 街で見かけた理不尽な叱り方・第1話
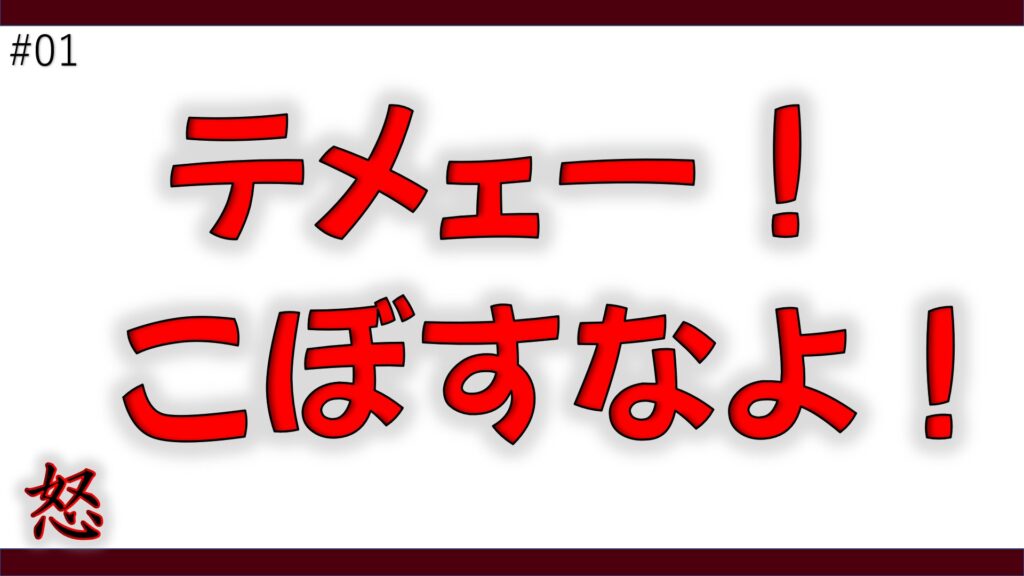
フードコートで、母親が、
「てめーこぼすなよ!」
と、2歳ぐらいの子に言っていました。
いや、無理でしょ!
これは間違いなく「暴言」ですね。
暴言が脳のどこに影響するか知っていますか?
「体罰」「暴言」「DV」で影響する場所が違うんです。
今日はそこを解説してみます。
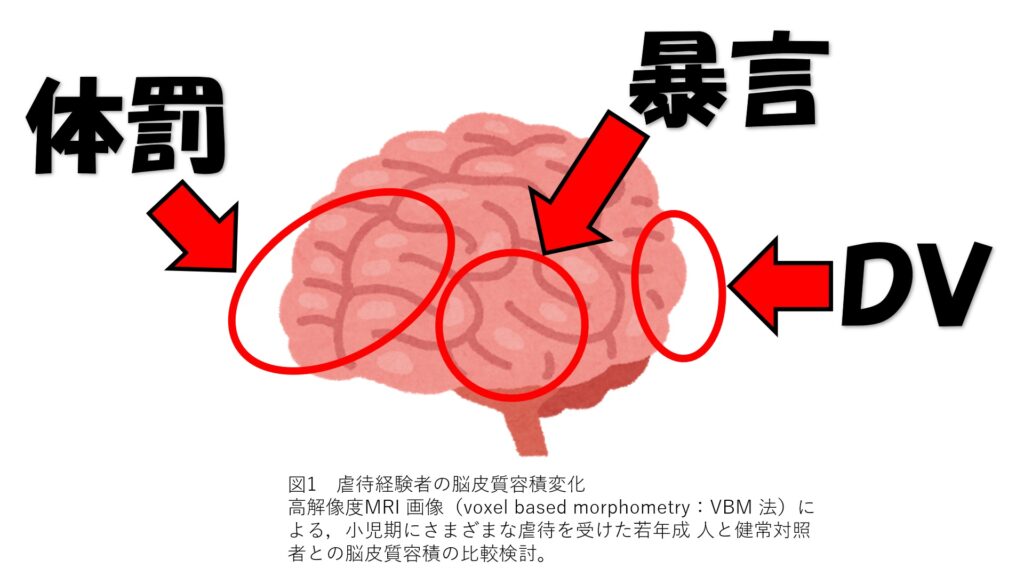

1.体罰の影響
体罰は前頭前野を縮小させます。
「おでこの裏」ですね。
ここは「考える」「感情をコントロールする」といった働きをします。
前頭前野が小さい子はシンプルにその働きが小さい子です。
つまり、「考えることが苦手」「感情をコントロールするのが苦手」
ということです。
学校や園などで問題を起こしたり、
世の中に出て犯罪を犯したりしやすくなると言われています。
「幸せ」とは反対の人生になりやすいということです。
「しつけ」として体罰をする親がいますが、「しつけ=自分で自分をコントロールする」ということが、かえって出来にくくなるというわけです。
人間は本能(防衛反応)に強く影響されますから、
叩かれないために言うことをきく。
バレないようにうまくやる。
バレなきゃいいんだ。
そういう方向に行ってしまいます。
これも「不幸」なことです。
ちなみに、福井大学の友田明美さんによりますと、「前頭前野の一部である右前頭前野内側部の容積が平均19.1パーセントも小さくなっていた(Tomoda et al,, 2009)」という研究結果があるそうです。

2.暴言の影響
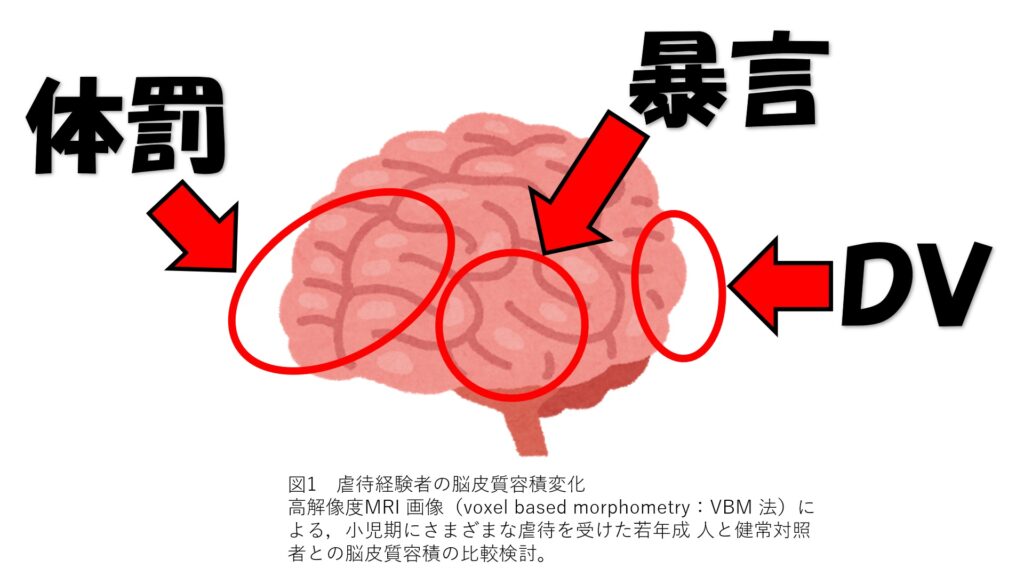
暴言は側頭葉の聴覚野を「ゴミ屋敷化」させます。
脳をグローブにたとえると、「グローブの親指」の部分が側頭葉です。
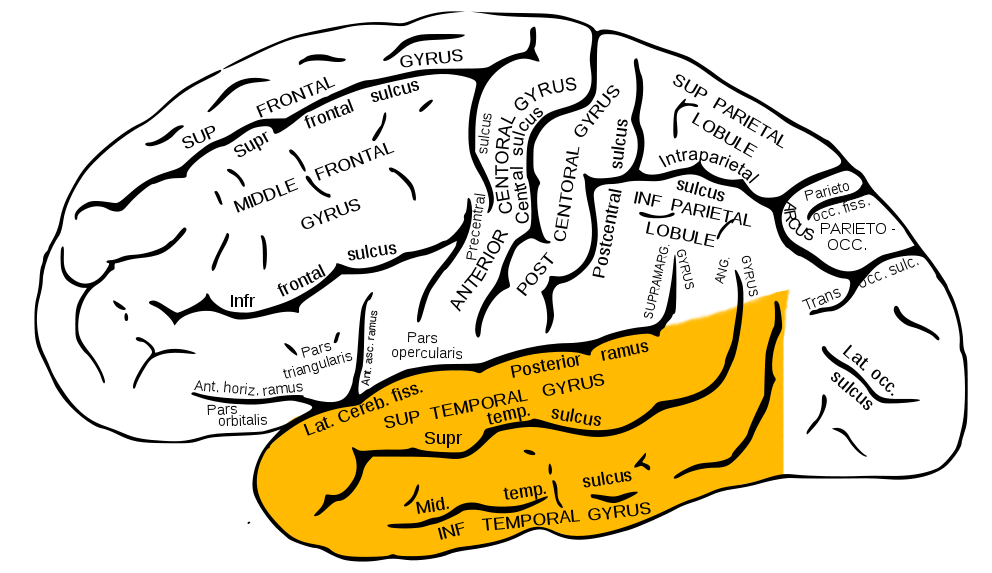
大脳の中で、「言語」「記憶」「聴覚」に関わっています。
簡単に言えば「コミュニケーション」ですね。
「死ね!」とか「ウザイ!」とか「てめーこぼすなよ!」とか…。
そういう言葉を浴びせられると、側頭葉が「ゴミ屋敷化」します。

どういうことかと言いますと、
側頭葉は幼児期に「刈り込み」と言われる整理整頓が行われるのですが、
その「刈り込み」が行われなくなっちゃうのです。

「刈り込み」というのは「芝刈り」や「雑草抜き」や「おかたづけ」みたいなものです。
要らない部分を片付けて、脳をスッキリ、使いやすくする働きです。
幼児は、様々な体験を言語化して、
「あ!これはこういうことだな!」
と、「理解」してゆきます。
脳は、この「理解」をする時に、「大事なこと」と「そうじゃないこと」を分けます。
「大事なこと」は脳の中で大きく育ち、
「そうじゃないこと」は刈り取られていくのです。
そして、ここがポイントなのですが、

この「刈り込み」は
安心安全のもとで行われるということです。
暴言を浴びせられると、不安や恐怖を感じて、刈り込みは行われません。その結果、「雑草だらけ」「ゴミ屋敷化」します。側頭葉の中がジャングルみたいになってしまうわけです。

こういう状態だと、人の話を聞いたり、会話をしたりするときに、他の子どもたちよりも集中して、時間をかけて、苦労して、話を聞かなければ「理解」が難しくなります。
言葉による理解がめんどくさくなる。
「普段からよく使う」「短い言葉」に頼ってしまうようになります。
もう少し大きくなった時も、こうした自分の「持ち駒」でしかコミュニケーションできなくなってしまうので、複雑な会話について行けなくなります。
友田教授は次のように書いています。
そして暴言の程度が深刻であるほど,影響は大きかった。暴言の程度をスコア化した評価法(parental verbal aggression scale)による検討では,同定された左上側頭回灰白質容積は母親( β =.54, p<.0001), 父親( β =.30, p<.02)の双方からの暴言の程度と正の関連を認めた。一方で,両親の学歴が高いほど同部の容積はむしろ小さいことがわかった(β=−.577, p<.0001)(Tomoda et al., 2011)『心理ワールド』80号「体罰や言葉での虐待が脳の発達に与える影響」

3.DVの影響

DVは視覚野に焼き付けられます。
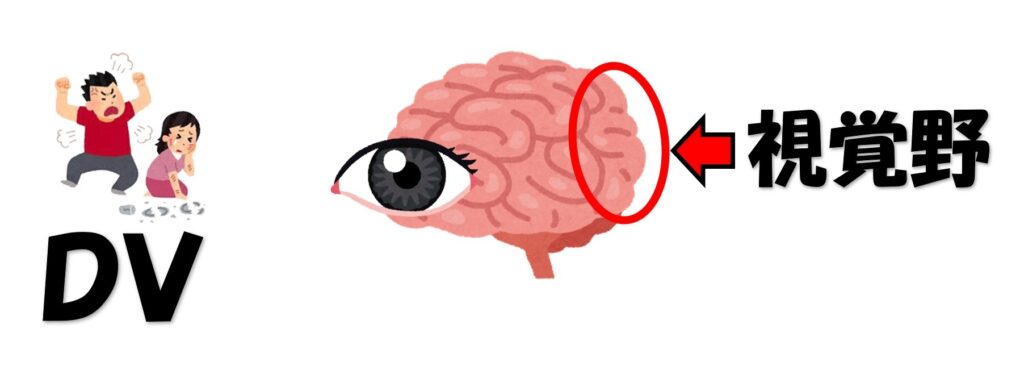
視覚野は眼球の奥にあります。
暴力シーンはそこに「焼き付け」られます。
トラウマですね。
興味深いのは、その影響は思春期になって現れるということです。
友田教授は「悪い影響が一番出やすい時期は,11歳〜13歳であることがわかった」と書かれています。(前掲記事)
幼児期の逆境体験はあとから顔を出す。
このことも知っておかなければなりませんね。


また、DV防止法では「心身に有害な影響を及ぼす言動」もDVに含まれていることから、「暴力」だけでなく、子どもの前での「暴言」も暴力にあたることになっています。
そして、暴言の影響は、先程紹介したように、聴覚野を「ゴミ屋敷化」させます。
暴力・暴言。DVは脳を様々な角度から痛めつけるのです。
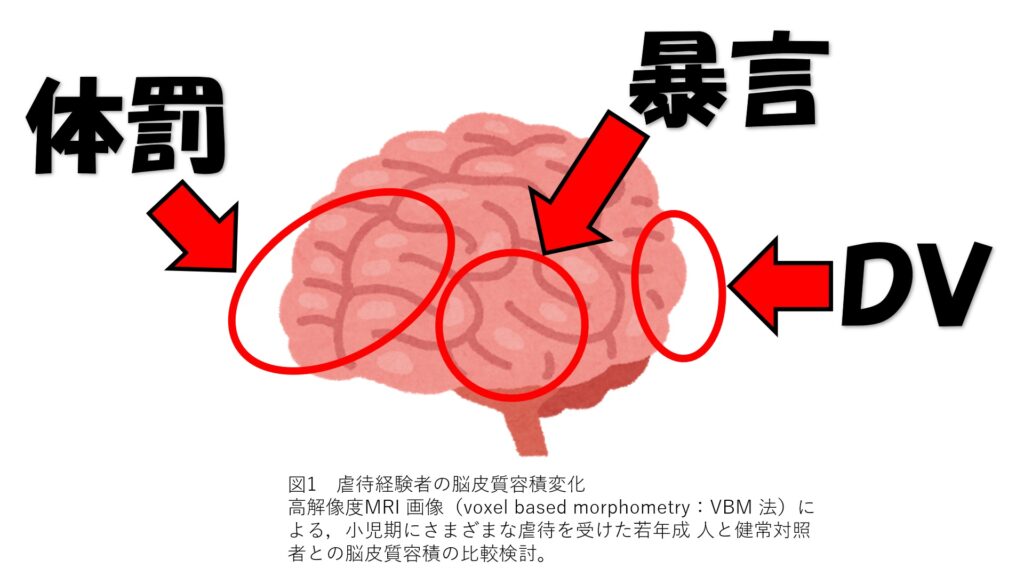
そして、多くの場合、その親は、
そんなことをしていることを知りません。
つまり、親本人だけの問題ではない、
ということです。
では、どうすればいいのか?
答えはシンプルです。
私たち大人が、
一人でも多く、
こうした知識を持っておくこと。
まずはここからです。
そうした大人が増えれば増えるほど、
いつかその知識は若い世代につながります。
私はそう信じて活動しています。





1件の返信
[…] 詳しくは、講座72「街で見かけた理不尽な叱り方・第1話」にあります。 […]