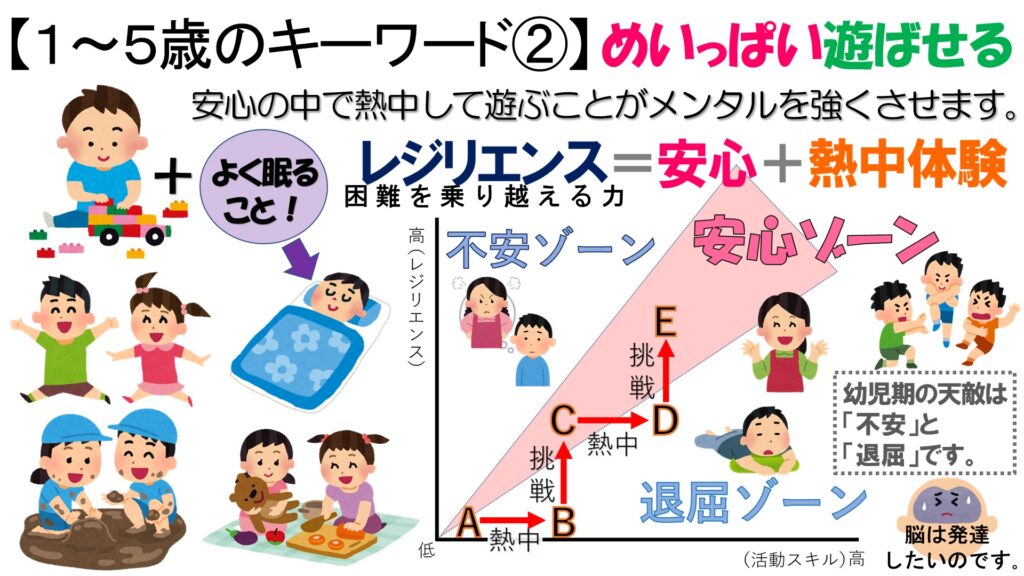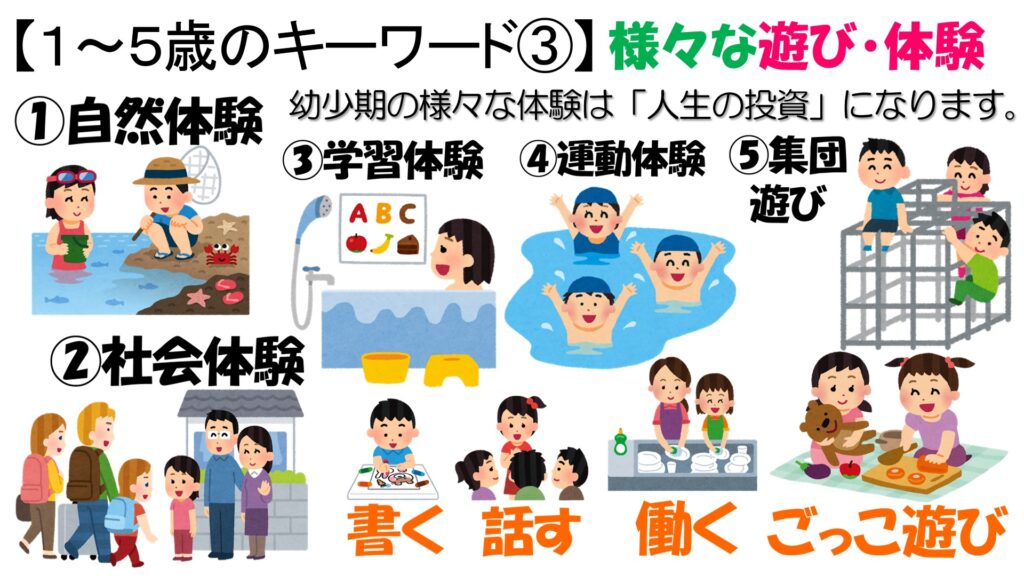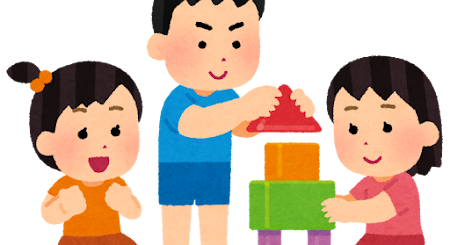講座192 「ゲーム障害」を考える

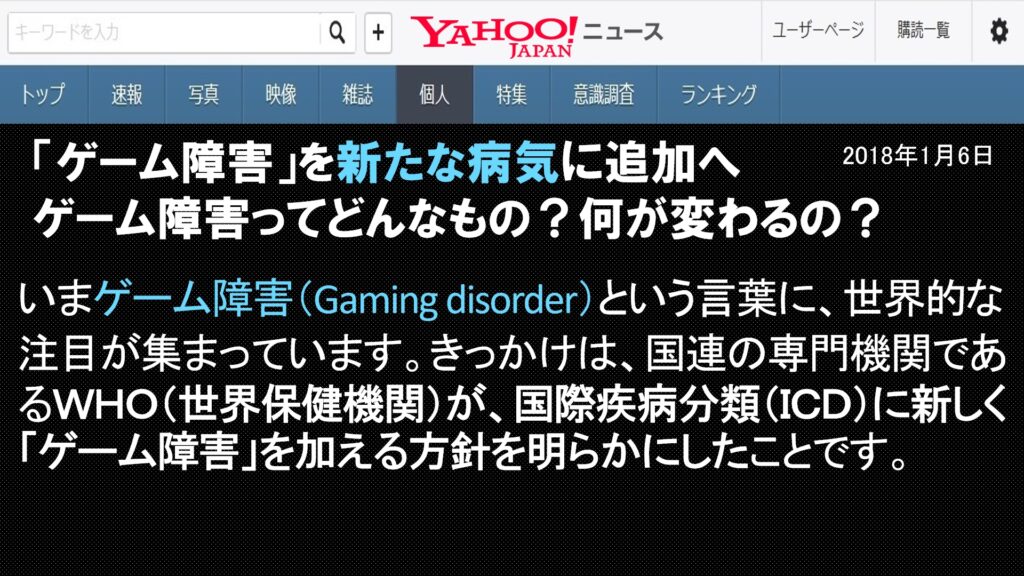
これは2018年のYahoo!ニュースです。
「ゲーム障害」が正式な病名として新しく認定される動きがあると報じています。
その後、2019年5月にWHOは認定しました。
こんな病気です。
ゲーム障害とは、ゲームをする時間をコ ントロールできない、他の生活上の関心事や日常の活動よりゲームを優先するといった症状が 1年以上継続することをいいます。 症状が重い 場合は1年以内でも該当します。
整理してみましょう。
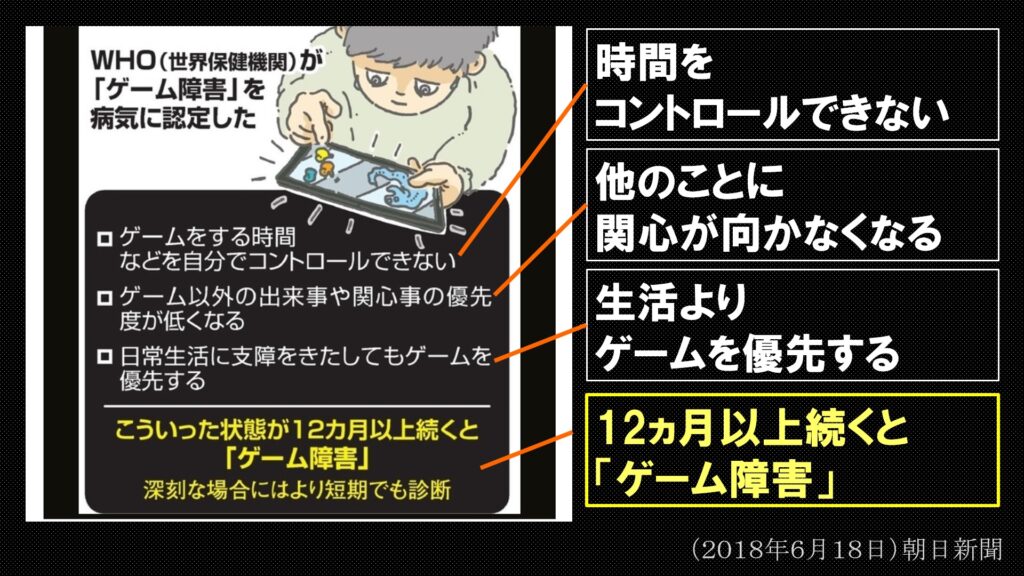
「時間をコントロールできない」
「他のことに関心がなくなる」
「生活よりゲームを優先する」
多くの子どもたちが該当しそうで怖いですね。
今回はこの「ゲーム障害」について考えてみます。
2.やめられなくなる仕組み・その②
3.大きな落とし穴
4.解決策
5.予防策

1.やめられなくなる仕組み・その①
①楽しいから!
ゲームはどうしてやめられなくなるのでしょう?
それは「楽しい!」からです。
この単純な理由に、実は、深い意味があるのです。
楽しいと脳の中でドーパミン(快楽ホルモン)が分泌されます。
このドーパミンは楽しいと出る物質ですが、次の性質を持っています。
長続きしない
そのため「慣れる」「飽きる」という現象が生まれます。
そうですよね。
いくら楽しいことでも、同じことのくり返しだと飽きてきますよね。
それがドーパミンの性質です。
普通なら飽きるんです。
しかし、ゲームには飽きさせない工夫が「これでもか」というほどあります。
慣れる間もなく次々に楽しさが襲って来ます。
これが、やめられなくなる仕組みの①です。
まあ、ほとんどの子はこの仕組みにハマってしまうでしょう。
でも、中にはこの仕組みから脱出できる子もいます。
それはどんな子かいうと、
他に楽しさを持っている子
です。
「ゲーム以外にも楽しいことがある」ということを知っている子です。
この逆が、ゲームから抜け出せない子、つまり、
他に楽しさを持っていない子
というわけです。
図にまとめます。
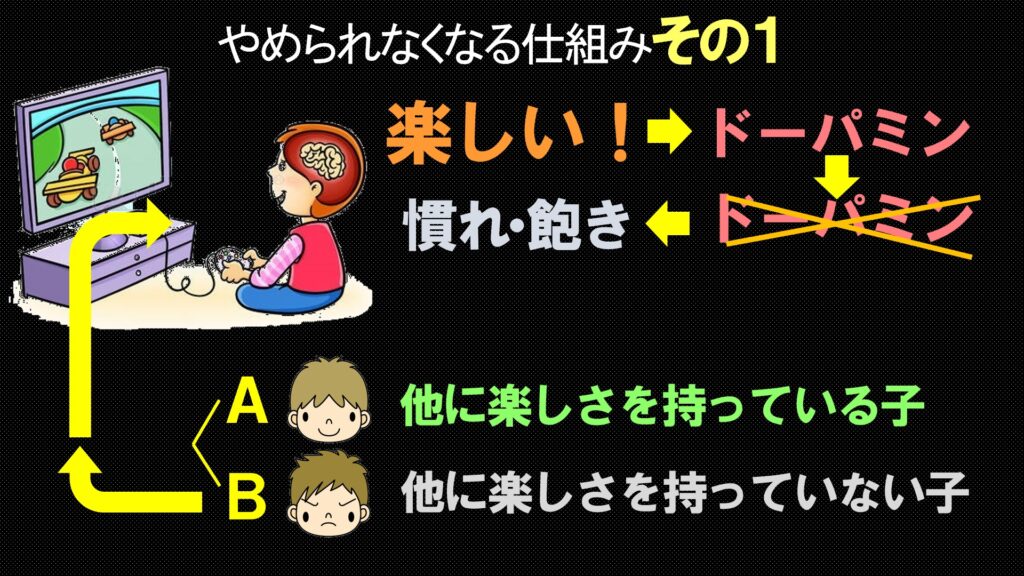
ゲームから抜け出すのは難しいことです。
なぜなら、ゲームには飽きさせない工夫があるからです。
B(他に楽しさを持っていない子)のほとんどは自力で抜け出せないはずです。
もし、抜け出せる子がいるとすれば、それは、
A(他に楽しさを知っている子)である可能性が高いのではないでしょうか。

2. やめられなくなる仕組み・その②
②おでこの裏が未発達だから!
子どもは「おでこの裏」、つまり前頭前野が未発達です。
どのくらいで発達するかというと24歳くらいです。
24歳くらいになると、
・我慢する力
・切り替える力
・全体を見渡す力
そういう能力が成熟してきます。
ですから、子どもは「我慢」が苦手です。
パッと気持ちを「切り替える」のも苦手です。
今がどういう状況なのかを「見渡す」ことも苦手です。
これがゲームをやめられなくなる仕組みの②です。
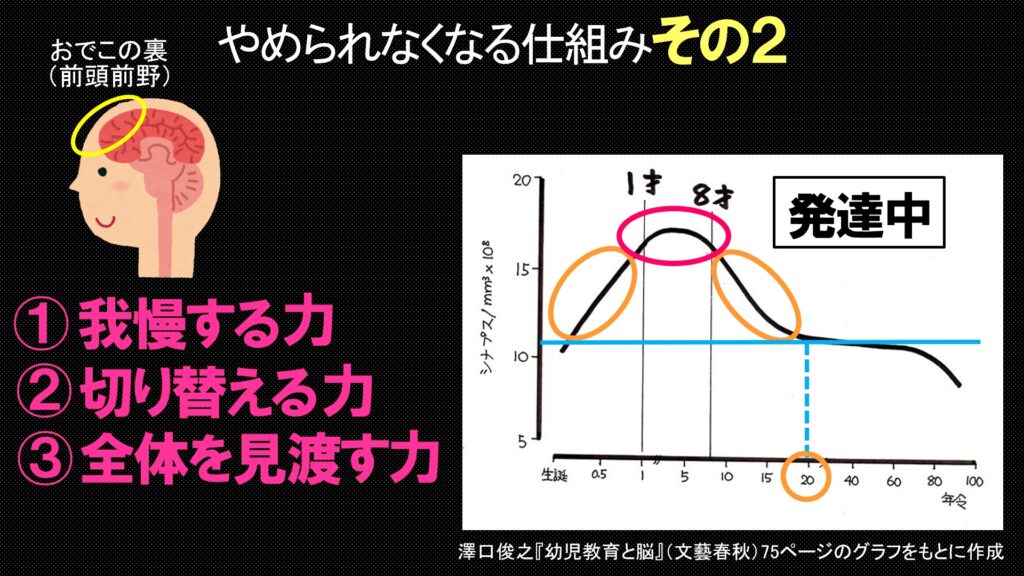
では、どうしたらいいのか?
答えは単純です。
「おでこの裏」を発達させればいいのです。
「おでこの裏」を発達させる方法は3つあります。
(1)言葉で考える経験をたくさんさせる
(2)熱中する体験をたくさんさせる
(3)様々な種類の遊びをたくさんさせる
(1)~(3)の経験を、できれば8歳までにすることです。
ゲームは熱中する体験に含まれますが、それだけだと体験が偏ってしまいます。
(1)~(3)をまんべんなく経験させることが理想です。
ですから、
ゲームだけをやっていると、ゲームから抜け出す力が育たない
という結果になってしまいます。

3.大きな落とし穴
ここまで、「ゲームをやめられなくなく仕組み」を解説してきました。
勘の鋭い方はもう気づかれたでしょうか?
この仕組みに基づくと、「あること」が浮かんで来ます。
それは、Aの子とBの子には大きな差があることです。
それが何か気づきましたか?
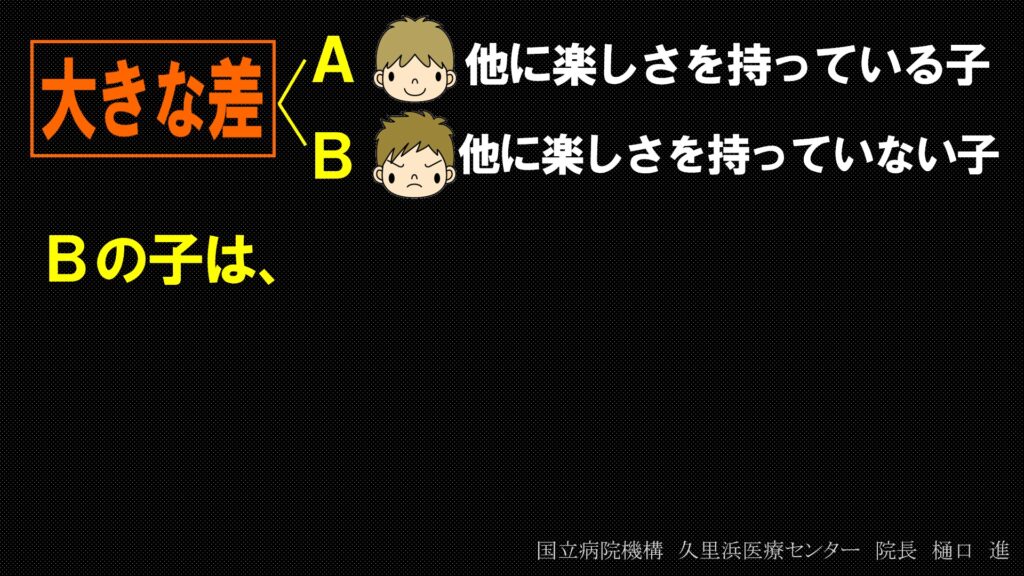
それは、
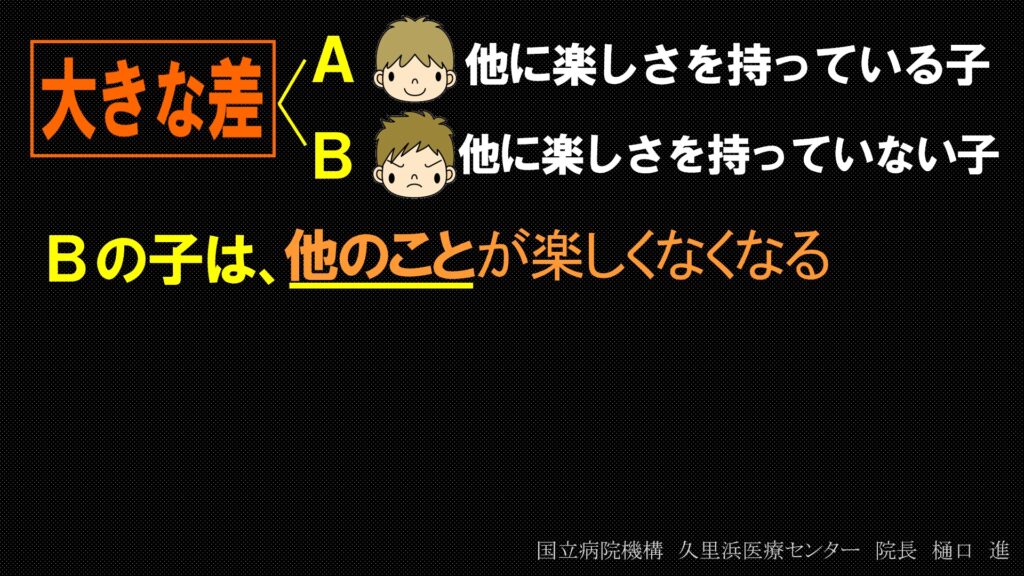
他のこと(ゲーム以外のこと)が楽しくなくなるということです。
ゲームから抜け出せない子は、どんどんゲームをします。
つまり、ゲーム以外のことをする機会を失うわけです。
A君は、1日1時間だけゲームをして4時間は他のことをして遊ぶとします。
B君は、1日5時間ゲームだけをして終わるとします。
一週間でどのくらいの差が出るでしょう。
A君:4時間×7=28時間他のこと
B君」0時間×7=0時間
「他のこと」が脳の前頭前野を発達させると言いました。
たった一週間の間にも、A君は「おでこの裏」をどんどん発達させます。
一方のB君はゼロです。ゲームに熱中できるというそのことだけです。
自分の行動を我慢したり、切り替えたり、見渡したりする機会が圧倒的に少ないわけです。
「大きな差」というのはそういうことです。
まだあります。
前頭前野の発達に差がつくだけではありません。
他のことが「楽しくなくなる」という点を見逃してはなりません。
これはつまり、
外遊び・運動・勉強・趣味・興味・好奇心・会話・家族団欒など、
様々なことが、
ゲームより、楽しくなくなる
ということなのです。
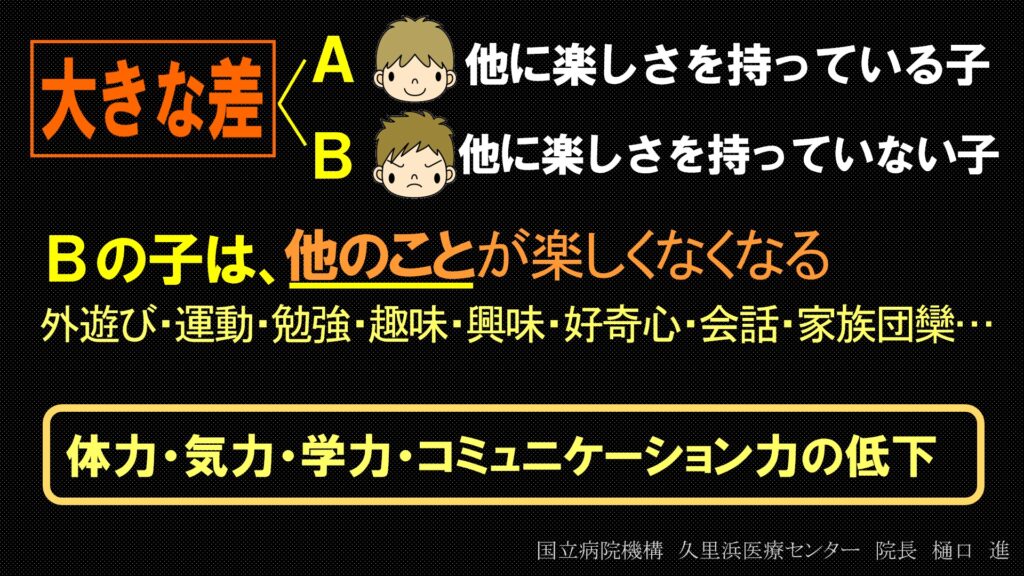
その行き着く先がどうなるかは想像できると思います。
体力、気力、学力、コミュニケーション能力などの低下です。

4.解決策
解決策はよく言われていることです。
一つは、ルールをつくることです。
ゲーム障害の専門医である樋口進先生が提唱されているルールは次の7つです。
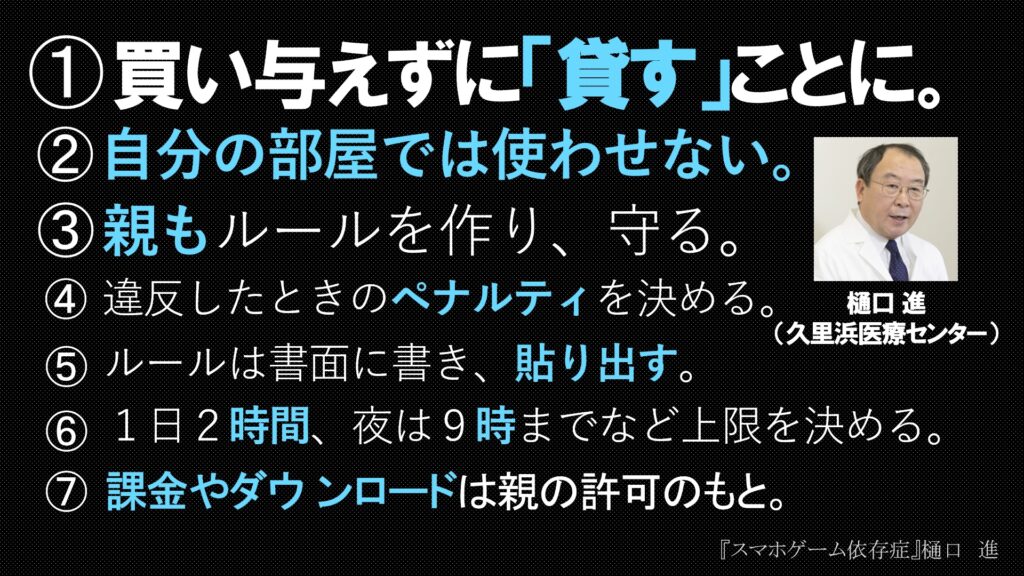
重要だと思える部分を大きくしてみました。
家庭の事情は様々ですから、無理せず、やれるところから取り入れることも大切です。
もう一つは、ゲーム以外の「他のこと」をやらせることです。
理想を言えば「楽しいこと」です。
すでにゲームの楽しさを覚えてしまった子には難しいかも知れませんが、
「ルール」+「他の楽しいこと」
が治療だと思って取り組むしかないでしょう。

5.予防策
お子さんが1歳~5歳の間は予防が有効です。
予防策はこの3つです。