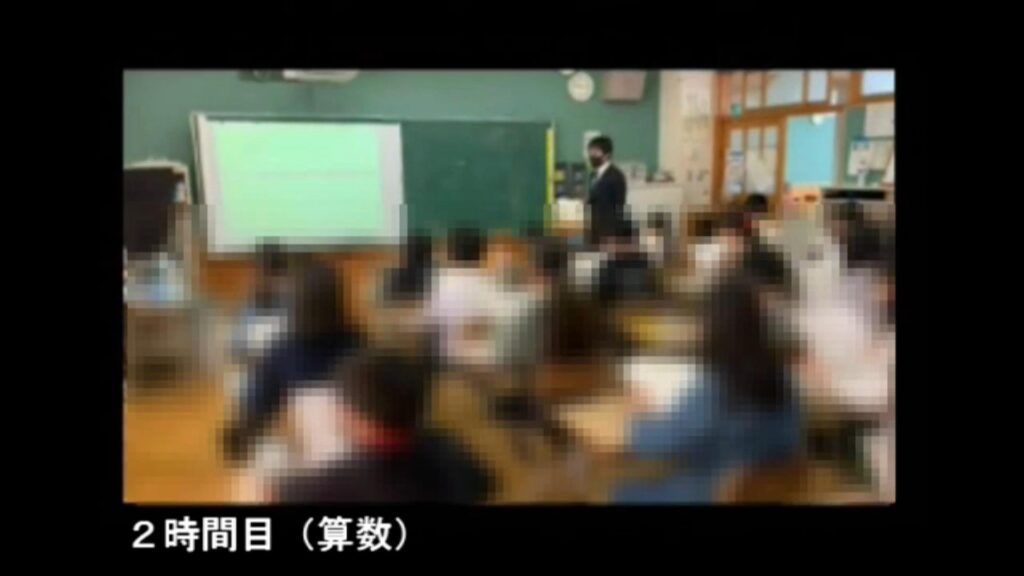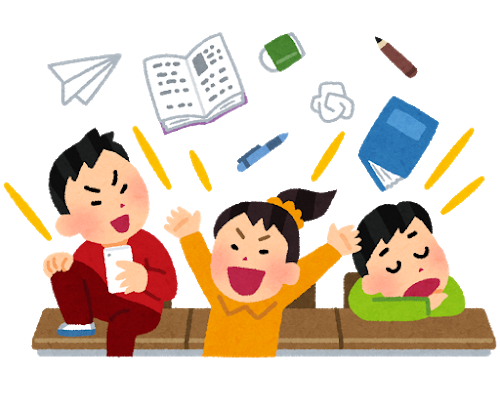講座111 学校の先生の「普通の一日」【解説編⑥】「全員」の教科書を開かせる
2.全員が教科書を開いたのはいつ?
3.まだ「全員」ではない
4.全員の参加態勢が整う

まずは前回の動画をご覧ください。

1.前回のまとめ
あいさつをさせるでもなく、席に着きなさいと言うのでもなく、
先生の第一声は「158ページ」でした。
第一の理由は、「授業を始めるよ」という合図を送るためです。
第二の理由は、ページ数を伝えるためです。
しかし!
それだけで全員が教科書を開くかなんて、とんでもない大誤解です。
①教科書を机の上に出せない
②ページを開けない
③問題番号を見つけられない
④ノートに写せない
⑤終わった後に何をしたらいいか分からない
教室には、こういう所でつまずく子が「クラスに1/3くらい」います。
「こういう所」というのはいつも同じではありません。
同じ子が、いつも同じ所でつまずくわけではないのです。
こうした子は「学習習慣」「学習技能」が身についていないのです。
したがって、授業のいろんな過程でつまずきます。
算数の勉強が出来ないという子は、算数ができないのではない。
特に、算数という教科は教科書を使う教科ですので、
そうした子への配慮が必要になります。
ここまでが前回の話でした。

2.全員が教科書を開いたのはいつ?
教師は子どもたち「全員」を相手にしています。
一人も漏らさず授業に参加できるように配慮します。
では、さっきの動画で、全員が教科書を開いたのはどの段階か指摘できますか?
今回はそのことを解説していきます。
先生が発した言葉を書き出してみます。
【0:11まで】
158ページ、シカク6。
次のような立体の名前を書きましょう。また、展開図を書きましょうという問題です。
「158ページ」と発した時には数人の子がまだ立ち歩いていました。
「という問題です」と言い終わった時には全員が着席していました。
先生はもう一度問題を読み上げます。
【0:20まで】
次のような立体の名前を書きましょう。また、展開図を書きましょう。
「次のような」さんはい。
さっきと読み方が違います。少しテンポが速くなっています。
なぜだかわかりますか?理由を説明できますか?
さっきの場面では立って歩いている子がいました。
その子たちが席に着くまでには「少しの時間」がかかります。
その時間を確保するために、一回目はわざとゆっくり読んだのです。
つまり、
席に着いていなかった子たちには「授業を始めるよ」という合図として、
すでに席に着いている子たちには「158ページ」ですよという指示として、
一回目はゆっくりだったわけです。
しかし、二回目の時には全員が席に着いています。
今度は授業を加速させなければなりません。
同じ調子で読んだなら、最初から着席していた子の緊張感は途切れます。
また、この二回目は「次に問題文を読ませるため」という意図もあります。
「今、先生が読んだ所を次は皆さんが読むんですよ」という暗黙のメッセージがあります。
ですから、そのメッセージさえ伝わればよいのです。速くてよいのです。
そして、ここが一番重要なのですが、
まだ全員は教科書を開いていません。
そうですよね。やっと着席した子たちがいますから。
しかも彼らは机の上に教科書を出していません。
机の中から教科書を探し出す作業から始めなければなりません。
皆さんはこの「机の中から教科書を探し出す作業」をイメージできますか?
ここにも配慮が必要です。
往々にしてこういう子は机の中がぐちゃぐちゃです。
ぐちゃぐちゃの中から「算数」の教科書とノートを探さねばなりません。
1~3年生の間に、プリントばかり使った授業、画用紙ばかり使った授業をしていると、
作業が苦手な子は高学年になってもこうした所でつまずきます。
プリント学習なら自動的にプリントが配られますし、
画用紙による問題提示なら教科書を出さなくて済むからです。
このような授業は、教師にとっては楽です。
「教科書を出させる」ところから始めなくて済むからです。
しかし、そのことは作業な苦手な子どもたちをいつまでも苦手なままにします。
「学習習慣」「学習技能」を身につける機会を奪ってしまうわけです。

3.まだ「全員」ではない
子どもたちが読みます。
「次のような立体の名前を書きましょう。また、展開図を書きましょう」
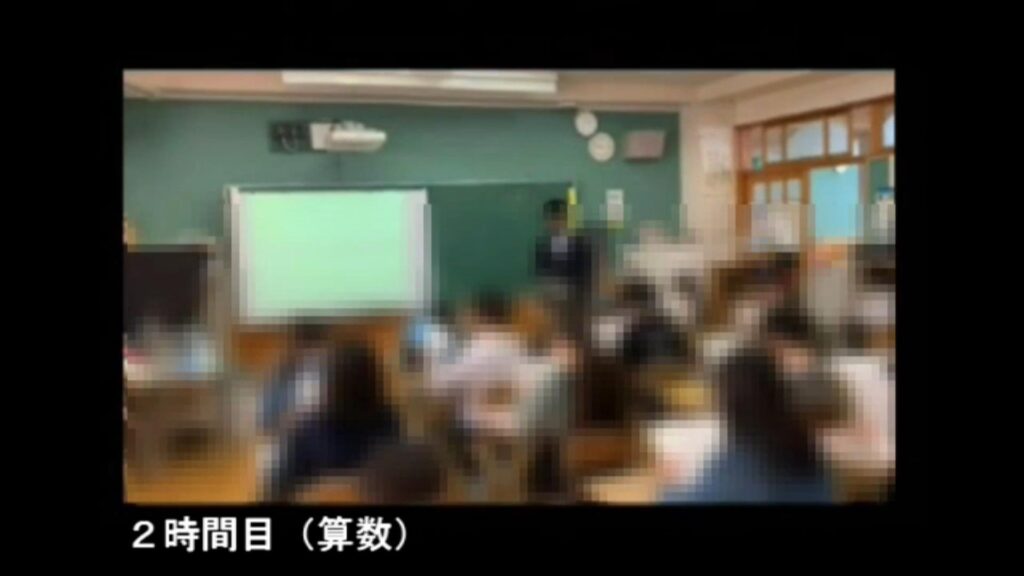
教科書を手に持って読んでいる子が増えました。
しかし、問題文を読んでいたのは「全員」ではありません。
「全員」というのは本当に全員でなければなりません。
「一人も漏らさず」ということです。
なぜなら、そこに追いついていない子ほど大切にしなければならないからです。
子どもたちが読み終わった直後に先生は言いました。
【0:30】
お隣さん読んでますか?
お隣さん読んでるよって人、手をあげてごらんなさい。
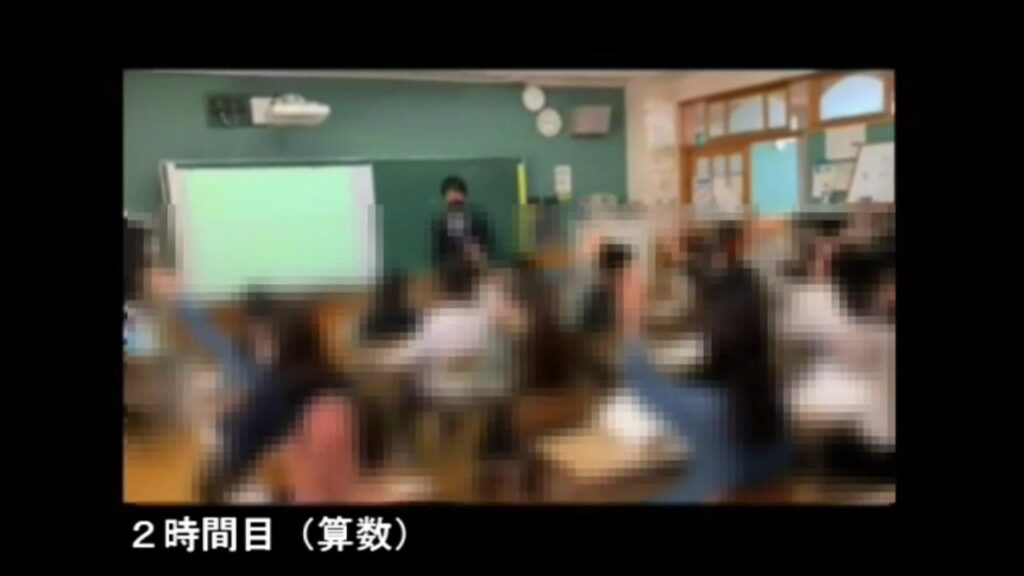
「隣の子は読んでいましたか?」という確認です。
本人確認ではなく、隣の子に確認させているのです。
まだ読んでいない子にとってはプレッシャーですね。
まだいるのです。追いついていない子が。
この場面では「確認」と「追い立て」をおこなったわけです。穏やかな声で。
【0:35】
読んでなかったよという人がいるようなので、もう一回読んでみましょうね。
何の理由もなく、もう一回読ませると授業はだらけます。
「なんだよ、また読むのかよ」といった感情が湧きますよね。
しかし、この場面では、なぜもう一回読むのか、その意味を伝えています。
これを趣意説明と言います。
「読んでいなかった人がいるようなので」というわけですね。
そして、すぐには読ませませんでした。
一番前の席の男の子に「何ページだっけ?」と聞きました。
その子がページ数を答えます。
先生は「よーし!えらい!」と言ってその子をほめます。
一番前の席の男の子はページ数を言っただけでほめられました。
ちゃんと教科書を開いて、授業についてきていることをほめられたわけです。
これは、この子への評価であると同時に、まだ教科書のページを探している子への支援です。
授業の中で先生が「ページ数」を口にしたのは、冒頭の第一声の時だけです。
その時はまだ立ち歩いている子がいました。
その子たちは席に戻るまでの間でしたページ数を耳にしていません。
何ページなのかを確かめさせるために、
敢えて時間をとって、一番前の席の男の子にページ数を言わせ、その子をほめ、
それからもう一回読ませたわけです。

4.全員の参加態勢が整う
子どもたちは声をそろえて読みました。
「次のような立体の名前を書きましょう。また、展開図を書きましょう」
最後の「書きましょうっ!」は、少し興奮した読み方をしていた男子がいましたが、
これはこのクラスにはやんちゃな男の子がいるという証ですね。
そして、その子も参加しているという証でもあります。
この時、はじめて全員がそろったわけです。
そして、ここから、授業は、その内容へと進んでいきます。
学校の先生の日常の授業は、このように進められているわけです。