講座325 向山家の子育て【法則②】叱らない
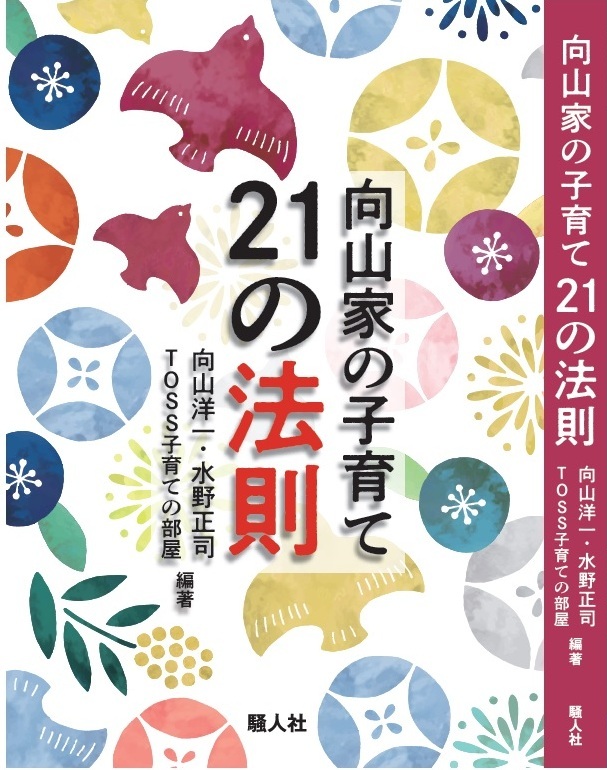
法則② 叱らない

向山洋一氏は、はっきりと書いている。2ページにわたる文章の中で、その後三度も「叱られなかった」と書いている。(67ページ)
そんなことがあるでしょうか。
叱らないで育てる
できるでしょうか。
もしかしたら一度くらいは叱られたのでは?
つい、そんな風に思ってしまうのですが、そんなことはどうでもよいのです。
大切なのは我が子が「叱られなかった」と強く記憶しているということ
「お母さんからよく叱られた?」
と聞かれた時に、あなたのお子さんはどう答えると思いますか?
普通は、叱られた時の記憶が強く残るものです。
どんなにたくさんほめて育てても、一回だけ叱った時の記憶の方がまさってしまうことだってあります。
それなのに「叱られなかった」という言葉が出て来るというのは、その子の親が「叱らない子育て」をしていたという証拠だと思います。
試しに我が子に尋ねてみてください。
「お母さんはあなたのことをよく叱ると思う?」
これはもう聞いた時点で素敵な親子のコミュニケーションが生まれるはずです。

今から10年前のことです。
小学館の教育雑誌『総合教育技術』2012年6月号が「『叱って育てる』教育の復権」という特集を組みました。
びっくりです。大手教育出版社がこんな特集を打ち出すなんて。
びっくりしているだけでは済まされません。
ただでさ叱ることが多いと言われている学校現場に、さらに叱る教育が広がったら大変です。
私たちTOSSは急遽『教育トークライン』臨時増刊号を出して徹底検証しました。
『徹底検証!「叱って育てる教育」VS「教えてほめる教育」』(東京教育技術研究所)
この本の中で小嶋悠紀氏は年間1000名以上の発達障害の子どもたちを診ている小児科医長に質問をぶつけています。
要約してその中の3つを紹介させていただきます。
Q1:「泣いたって終わらないんだよ。次どうすんの?」と聞く。泣かせた方がいい。
悲しいかな「あるある」ですね。
こういう叱り方、見たことがあります。
家庭でもありそうですね。
こういう叱り方に対してドクターはどう判断するか。
A1:率直に申し上げて効果はないと思います。
これは、この言葉をそのまま先生に返したいですね。
「泣かせたって終わらないんだよ!どうすんのって聞かないで教えてやれよ!」
こういう先生って、子どもに言わせようとするんですね。
子どもが泣いて困っているのに言わせようとする。
子どもが悪いという態度を出しまくっています。
子どもが悪いんですか?
間違いや失敗をするのが子どもじゃないですか?
それを活かすのが先生じゃないですか?
この先生は活かすどころか困らせている。
私たちTOSSの教育方針は明確です。
教育は、教えて、ほめる。
ダメなのは、教えないで、叱る。
「次どうすんの?」なんて、教えないで叱る典型ですね。

Q2:「5つほめて3つ叱れ」などのバランスが大切です
これ、ホントですか?
私は『叱り方大全』という本を出していますが、こんな割合のことは書いたことがありません。
断言します。
A2:バランスではなく叱り方が問題なのです。
グチグチ叱らない。短くスパッと叱る。
「叱られた」と思わせないくらい短いのがいいのです。
多くの先生方はこれと逆です。
「叱られた」と思わせるために長くグチグチと叱る。
子どもが悪いとでも思っているのでしょうか。
悪い子なんていないのに。

Q3:躊躇しちゃいけない!叱られることで子どもは強くなるんだ!
これも「あるある」ですね。
この場合も次の2点をチェックしなければいけません。
①教えているか?(叱るだけになっていないか)
②その叱り方はどうか?(短いか)
臨時増刊号の中で紹介されている作業療法士さんのコメントが分かりやすです。
先生が実践されている通り、「ほめる以外に何が子どもを伸ばすのか」と思いますね。例えば、ある人に言われた言葉ですけど、10歳のお子さんがいたとしますよね。発達障害でずっと叱られて来たという。その子はもう10年間叱られてるんですよね。10年間叱られた子どもと10年間ほめられた子どもと、どっちが伸び伸び生きますかって言ったら、どちらをやるべきか明白ですよね。
明白ですよね。
そして、伸び伸びと育ったその子は言うでしょう。
「私は母親から叱られたことがありません」と。

叱り方の具体例はこちらの動画から。詳しい解説は本からどうぞ。

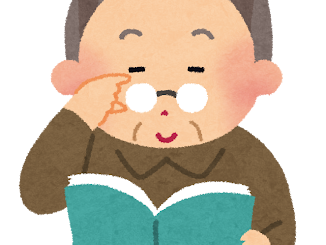

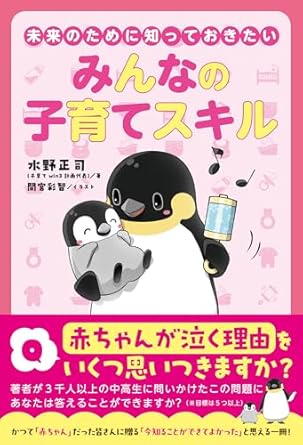

以前、『叱り方大全』を購入して読ませて頂いて理解はしていたものの、今この記事を読んでからもう一度読んでみると、ダメな叱り方のほとんどを最近やってしまっていました…。
最近忙しくて、子どもの行動を改善する以前に、自分自身の感情のコントロールもまだできていないことが分かりました。
定期的に読み返すことが大切ですね…。
自分自身。大事ですね!
自分ファーストで行こう!
特にお母さんは!
とても分かりやすかったです。以前、皆の前で詰問する教師がいました。結果、本人ではなくそれを見ていた子の保護者から苦情が届きました。曰く「友達が怒られているのを見るのがつらいから学校行きたくない」。それは小学校だから起きているのかと思いまいましたが、おそくら中学生でも同じだったでしょうね。
コメントありがとうございます。
感受性の強い子はそうなりますよね。
DVと同じですね。
動物には怖い思いを忘れないようにする仕組みが備わっているそうです。
私は自分の娘にそうさせてしまいました。
自戒を込めて。
仲の良いお母さんとお話しをしていて感じたことです。
どうやら、お母さん方は「叱る」ではなく「怒る」ことが多いようです。特に小さいお子さんがいるご家庭は、お母さんが寝不足な上に子どもが危険なことをしている!という事が度々起こるようです。お母さん目線だと、心にゆとりがなく、ついつい「コラー‼︎」とか「さっきも言ったでしょー‼︎」となってしまいがちになります。しかし、これでは子どもにとってもお母さんにとっても良いことは無いな、と思います。お母さん自身が『自分の機嫌を自分でとる』ということがまず大前提で、そこから「叱る」という行動ができるのだと思いました。
仲の良いお母さんとのお話しやこの本の内容をふまえて、私も自分の機嫌の舵を自分でとって頑張ります!
沙幸さんのコメントはとても重要です。
叱ることが出来ずに怒ってしまうお母さんは育児障害を起こしていると考えられます。
本来なら母親は直感的に育児できる能力を備えているのですが、社会環境によってその能力を発揮出来ない場合があります。
スマホ授乳などがその例です。
自分が怒鳴られて育ったという経験もその例です。
イライラしてストレスから怒ってしまうのもその例ですね。
育児障害を引き起こさないためには、そうした環境に負けない強さを持たなければならない社会になっています。
それには教育の力が必要です。
自分で勉強されているお母さんは大丈夫でしょう。
でも、学校を出て勉強嫌いになってしまった大多数のお母さん方はその環境に負けてしまいがちになります。
ですから、そうなる前に、子育ての仕方を学校教育で教えるべきだと思っています。
最近のお母さんたちは忙しすぎます。
忙しいが故に、怒鳴ってしまうこと多々あると思います。
私もそんな1人です。
そうなってしまった時は、引きずらないように自分を制御するようにしています。
ちょっと離れて(私はトイレに行きます)落ち着いて戻ってきたときには、いつものお母さんになるようにしています。
良くないとは分かっているけれど、感情に負けてしまいます。
おおらかに子どもに関わっていきたいです。
現在の日本は母親への負担が大き過ぎると思います。
かつては村全体で子供たちの世話をしていた仕組みがなくなり、
一気に、欧米化・近代化してしまったのが原因だと思っています。
これから、その反省に立ち、ちょうどいい仕組みを作り直す時期です。
今はその過渡期。
これ以上大変にはならない。させない。
そう思います。
「お母さんはあなたのことをよく叱ると思う?」
聞いてみました。
次男「うん、よく叱る」
長男「う〜ん・・・、まあ、叱るかな。褒めることもあるけど」
反省です。
特に次男は、即答でした。
次男に対して、厳しいことが多いなぁと、自分でも反省していましたが、
「よく叱る」
の言葉に、私もショックを受けました。
これを機会に、意識して褒めて、私も上機嫌にすごします!!
みほさんが言われたら、もう世界中のお母さんがアウトになります!