講座50 発達障害の「告知」8割が母親
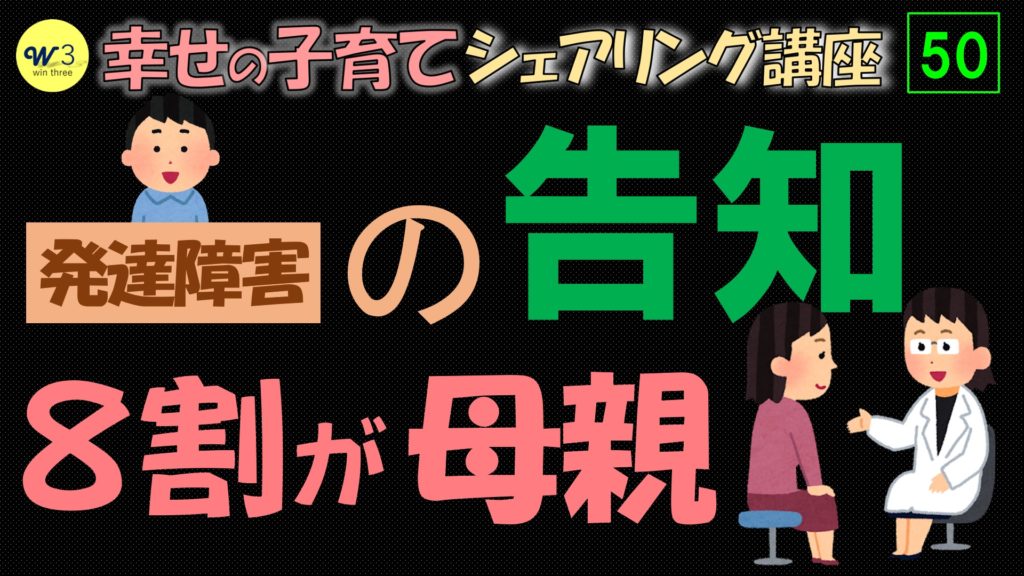
2.「告知」の現状
3.提案・「告知」のシステム
1.「診断」は誰がする?

発達障害の診断は誰がするのでしょう?
それはお医者さんです。
発達障害の診断ができるのは「医師」だけ
ですから、病院を受診しなければ診断はできません。診断しなければ薬も出せません。

学校の中には「発達障害」に詳しい先生がいるかも知れませんが、教師に診断はできません。

また、地域には心理士やカウンセラーなどの専門家がいると思いますが、「検査」は出来ても「診断」はできません。
医師であっても「発達障害の可能性があります」といった表現をします。
ですから、医師以外の人が「この子は発達障害かも知れない!」と簡単に判断することは出来ません。

2.「告知」の現状
診断とは別に「告知」という言葉があります。
一般的には、「本人に告げること」を告知と言います。
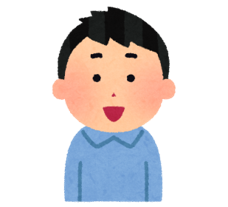
「あなたは発達障害なのですよ」
「おまえはADHDなんだよ」
そういうことを告げるのが「告知」です。
この「告知」には、誰がするという決まりがありません。
では、誰が本人に告知しているのでしょう?
それとも、告知はしない方がいいのでしょうか?
東京成徳大学の研究論文によると、約8割の場合「母親が」子どもに告知をしているといいます。(出典:「発達障害者への告知に必要な支援とは?」)
東北福祉大学の実態調査でも、「多くは,母親が告知を行っていた」と報告されています。(出典:「発達障害児本人への診断名告知について考える」)

告知は専門家でも難しいことだと思いますが、保護者に任されているのが実情のようです。
みなさんは我が子に発達障害の告知をする自信がありますか?
発達障害以外の病気や障害については、小児がん以外は「告知」するのが一般的になっています。(「発達障害児本人への診断名告知について考える」)
しかし、「小児がん」と「発達障害」については相手が子どもなので告知すること自体がデリケートな問題として残っています。
(1)告知すべきか/しないべきか?
(2)するとして、いつするか?
(3)誰がするのか?
こうした問題が「保護者任せ」になっているのが現状です。
したがって、このような問題に悩まれている保護者は多いはずです。

3.提案・「告知」のシステム
(1)~(3)についての私の考えを書きます。
(1)告知すべきか/しないべきか?
私の考えはシンプルです。
提案(1)成人するまでに告知すべき
成人するまでは保護者に義務がありますが、成人したら親の手を離れます。
少なくとも親の手を離れる前までには伝えてあげるべきだと思います。
(2)するとして、いつするか?
発達障害情報支援センターのWEBページには「本人に伝えるタイミング」が4つ書かれています。
①まわりの同年代の子どもとのちがいに気づき始めた学童期
②学業や友人関係につまずき自尊心が低下した思春期
③進学や就職など適性に沿った進路選択に悩む青年期
④職場での対人関係や仕事が思うようにいかない成人期
この4つについては「どうとらえるか」が重要になります。
できるなら、④の「職場での人間関係」で困る前に伝えてあげるべきだという考えもあります。④が原因で病んでしまう人もいるからです。
また、できるなら、③の「進路選択」の前に伝えてあげるべきだという考えもあります。自分の進路ですから、子ども自身が自分の特性に合った進路を選ぶべきだという考えがあるからです。
そうなると、②「思春期」と①「学童期」が残ります。
学童期というのは小学生という意味です。
小学生と言っても、低中高と6年間あります。低学年や中学年では告知しても本人が理解し、受けとめられるかどうかが疑問です。告知するにはある程度の理解力が欠かせません。
告知しても本人が理解し、受けとめられるかどうかが問題になります。
提案(2)小学校高学年~中学3年生までには告知すべき
(3)誰がするのか?
「現状8割が母親」ですが、私は「母親だけ」というのは荷が重過ぎると思います。母親や父親という保護者の存在または同意は欠かせませんが、できれば専門的な知識のある第三者が告知すべきだと考えます。
提案(3) 専門的な知識のある第三者が告知すべき
告知は衝撃的な出来事であり、子どもはセンシティブな年齢です。
そして、告知後も24時間一緒に過ごすのは保護者です。保護者は「子どもを安心させる存在」であり続けるべきです。
保護者を、障害についての説明をする立場には置かず、子どもの不安や悩みを共に抱える立場に置くこと。これが最優先されるべきです。
したがって、「母親8割」の現状は望ましい状況ではありません。
私が「第三者」を提案する理由はそこにあります。
ただし、
告知直前までの時間は、保護者と第三者が連携していなければなりません。
チームを組む必要があります。
そして、チームを組むためには、保護者にも「発達障害」についての知識が必要です。
「第三者」は、子どもが置かれている環境によって異なるでしょう。医師、心理士、学校の先生、児童館の先生などケース・バイ・ケースです。 幼児であれば子育て支援包括センターが総合的な窓口になっています。
告知には長期的な準備が必要です。
早めに第三者と相談すること。
相談とは「作戦会議」です。
チームを組んで取り組んでください。
そのためには保護者の側にも知識が必要です。
①早目に相談してチームを組んでおく
②保護者も勉強して知識を得ておく
いつか来る「告知」のためにこの記事を活用してください。




