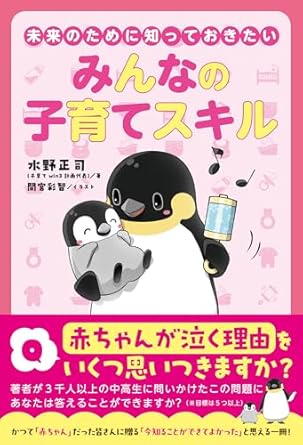講座321 QA⑨「発達障害」と(発達障害)
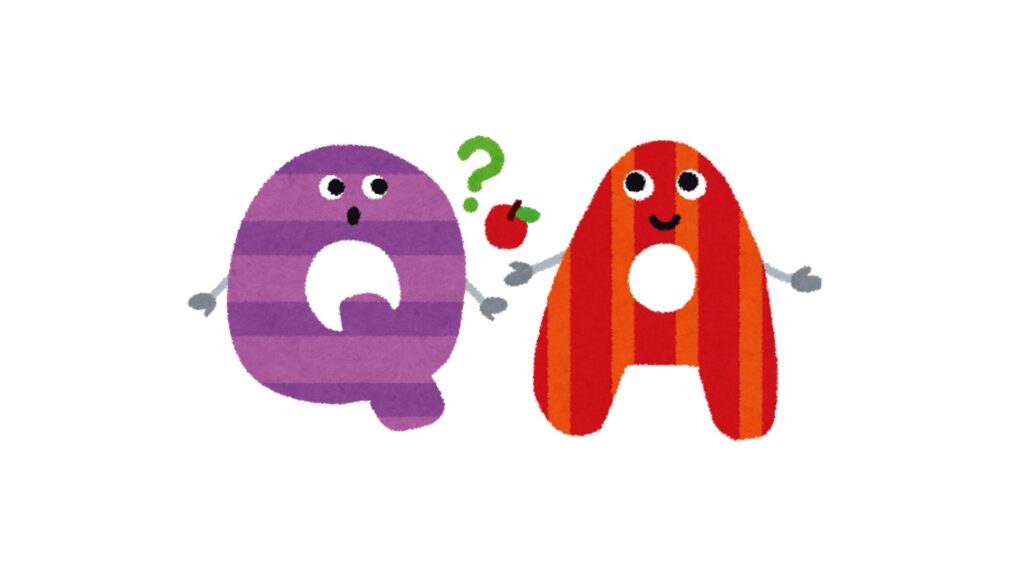
Q9 大人になってから発達障害になることはないというのは本当なのでしょうか?
これはですね。
「大人の発達障害」という言い方に問題があるのです。
なぜ、わざわざ「大人の」と付けるのか?
発達障害が「子ども特有の障害」だと思われているのでしょうか?
そのへんを整理してみます。
1.「発達障害」と(発達障害)
発達障害という言葉にはニ通りの使われ方が存在しているように思います。
一つは、正真正銘の「発達障害」です。
本人が持っている発達の凸凹に、社会的不適応が重なって生じる発達障害です。
このケースでは、医師が発達障害の可能性が高いことを診断するでしょう。
そういう意味での「発達障害」です。
もう一つは、新聞やテレビや世間の人が言う時の発達障害です。
これは本当の意味での発達障害ではなく、「世間が言うところの発達障害」という意味で、多少の凸凹やちょっと変わった個性に対しても、なんでもかんでも発達障害と言ってしまう場合の発達障害です。
私自身も、世間話をする時は、こっちの発達障害を使うことがよくあります。
言わば、カッコ付きの発達障害という感じです。
【本来】「発達障害」 【世間】(発達障害)
口で言ったら同じですが、頭の中では( )を付けているという感じです。
「全国学テ」と同じで、「発達障害」という言葉は、すでにある意味を持って世間に広まってしまっているので、それをなくすことは難しいと思います。
ですから、その使い方も認めながら、本来の使い方を広めて行きたいと思っています。

2.「大人の」の意味
それと同じように、「大人の発達障害」という言葉も独り歩きしているように思います。
なぜわざわざ「大人の」が付くのでしょうか?
この時に使われている発達障害という言葉は「発達障害」と(発達障害)が混じっています。
だからややこしいのです。
私は研修会の中で、「大人になって発達障害になることはありません」と言いました。
この場合は、世間で言う(発達障害)のことです。
話を世間に合わせたわけです。
(発達障害)はその人の個性です。
生まれつき持っているものです。
ですから、大人になってから(発達障害)になるという言い方はおかしな話です。
ここまでは理解していただけますでしょうか。
それと区別して、「大人になって本当の発達障害になる」ということならあり得ます。
子どもの頃には適応できていたのに、大人になったら適応できなくなったという場合です。
それがどんなケースか想像できますか?
講座316で「不適応を起こしやすい四つの場所」を示しました。
①園
②学校
③高等学校
④職場
大人になって発達障害になったとすれば、①②③は適応できていたのに、④の就職後に不適応が生じたというケースを想像できます。
そして、これを「大人の発達障害」と呼ぶのが本来の意味なのだと思います。
「大人の発達障害」ということかは、周りにいるチョット変わった人をいう意味ではないわけです。
今回私がこのテーマをいただいた時に、「わあー困ったなあ」と思ったのはこういうことです。
多くの一が知らないような新鮮な事柄を話すよりも、ある程度多くの人が知っている事柄を話す方が難しい場合があります。
今回は後者です。
「大人の発達障害」について理解していただけましたでしょうか。