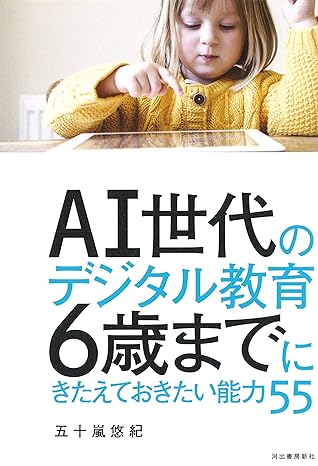『AI世代のデジタル教育・6歳までにきたえておきたい能力55』
今回ご紹介するのは、五十嵐悠紀『AI世代のデジタル教育・6歳までにきたえておきたい能力55』(河出書房新社)です。2017年の本ですから、この種の本としては古いものになってしまいました。当時はこういう本がブームだったように記憶しています。当時の折り目は30カ所。

今回、この本を紹介するにあたって読み返してみたのですが、コロナ禍の現在だからこそヒントとなる記述がいくつかありました。改めて読んでみるのもいいものですね。ひとつ紹介します。
つまり、好奇心、関心といった態度の部分に関して、遊びを中心に育てていくのが良いとされているのです。(37ページ)
そう言えばそうでした。非認知スキルは、いわゆる勉強ではなく、遊びで育つ部分が多いのでした。コロナ禍の今は、集団での遊びができませんが、ほかの遊びならできそうです。大事なのは「好奇心・関心」ですね。
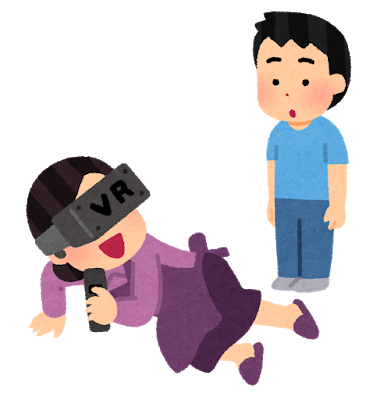
この方向でもう少し紹介してみましょう。
アメリカのテキサス州にある私立幼稚園でも、3歳からコンピュータの時間があるそうです。「ほとんど遊んでいるだけ」と通わせている親御さんは表現していますが、教育系アプリを用いて、担任とは別の、コンピュータを教える専門の先生のもとで、デジタルバイアスに触れているようです。(41ページ)
今、家の中でゲームや動画ばかり見ている子が多いようですが、コンテンツをちょっと変えるだけで、非認知スキルを育てる有用な遊びになる可能性は大きいと思います。本来は、勉強と遊びには境目がなかったはずです。いつから勉強は「楽しくないもの」になってしまったのでしょう。
この本をもとに、非認知スキルを伸ばすアプリの選び方を整理してみます。
①遊び方を自分で決められる余地のあるもの
②親も一緒にかかわる余地のあるもの
③時間を区切る余地のあるもの
④失敗する余地のあるもの
⑤工夫する余地のあるもの
こんなところでしょうか。
⑤の「工夫する余地のあるもの」というのが達成感を味わうことにつながるのだと思います。
最後に、もう別な観点から書き抜いてみます。
親が自分をどうとらえているかが、子どもにとっては大きい
家でゲームばかりしている子だったらどうでしょう。
その子の親御さんは我が子をどう思っているでしょう。
我が子をマイナスの気持ちでとらえているのか。
プラスの気持ちでとらえているのか。
毎日にのことです。
その違いは大きいような気がします。