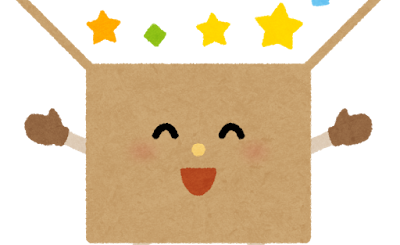『赤ちゃんと脳科学』
帯:「天才」になるより「幸せ」な人間に育てたい!
今回ご紹介するのは、小西行郎『赤ちゃんと脳科学』(集英社新書)2003年初刊です。折り目は2か所。

小西先生は日本赤ちゃん学会の事務局長をされた方で、「赤ちゃん学」という言葉を初めて使われた方です。折り目は2つですが、今につながる基本的なことが数多く書かれています。
生まれてすぐの赤ちゃんが理由もなく「微笑む」のと同じように、「泣く」ことも胎児期から備わっている能力なのです。私の観察では、胎児も自発的に泣いていることがわかっています。(19ページ)
私の講座に出て来る「泣くは能力」という考え方は、この本をはじめいくつかの書籍に書かれています。でも、胎児まで泣いているというのは初めて知りました。
1990年代は「テレビの影響」に関する研究が盛んでした。この本にも、赤ちゃんに対するテレビの影響が書かれています。

体動の引き込み現象
赤ちゃんは人の語りかけに対して手足をバタバタさせたりしますよね。

この時、語りかけた大人の方も無意識にうなずいたり笑ったりして反応します。
これが「体動の引き込み現象」と呼ばれるものです。(143ページ)
この現象は、赤ちゃんの「確認作業」だと言われています。どういうことかと言いますと、赤ちゃんと大人の間にコミュニケーションが成立していることを赤ちゃんが確認しているということです。
「あ!通じてる!」
と、赤ちゃんは実感しているはずです。
つまりは「成功体験」ですね。
いうまでもなく、こうした体験が脳の機能を発達させることになります。
ところがテレビだと情報の一方通行で反応がありません。当時の医師たちはこのことを危惧して「2歳まではテレビを見せるな」などと提唱していました。