講座500 愛着障害の今(1)

先日、2024年8月31日に、尊敬する杉山登志郎先生のセミナーに参加させていただきました。
テーマは「子育てと愛着形成の全体像を学ぶ」です。
会場が北海道で、テーマが「子育て」だったからだと思います。
私も講座を持たせていただくことができました。
今回はこのセミナーで学んだことと、杉山先生の最新刊である『トラウマ・「こころの傷」をどう癒やすか』から学んだことをもとに、「愛着障害の今」というタイトルで、何回かに分けて、発達障害と愛着障害に関する現状について書いてみます。

2.「カテゴリー診断」を疑う
3.薬物治療の今
4.学校教育の今
5.「発達凸凹」に対する無理解
6.まとめ

1.SUGIYAMAショック・発達障害におけるコペルニクス的転回
このセミナーを通じて衝撃を受けた《考え方》を列挙してみます。(文責;水野)
(1)発達障害の大半は、病気でもないし、障害でもない。
(2)小児科医や児童精神科医を受診する児童の9割以上が発達凸凹に過ぎない。
(3)DSM-5やICD-11のようなカテゴリー診断は非科学的である。
(4)学校の先生がいちばん苦労している児童の多くは「発達性トラウマ症」であろう。
(5)「発達性トラウマ症」を持つ児童の親の多くは「複雑性PTSD」の診断基準を満たす。
(6)児童虐待の連鎖率は7割を超える。
(7)10年後くらいには、今の発達障害の診断基準は意味をなさなくなるだろう。
どうですか?
衝撃を受けませんか?
そして、これらのことを説明できますか?
これから、これらの《考え方》について解説していきたいと思います。
(「思います」と書いたのは、解説できるかどうか自信がないからです)

2.「カテゴリー診断」を疑う
(1)発達障害の大半は、病気でもないし、障害でもない。
(2)小児科医や児童精神科医を受診する児童の9割以上が発達凸凹に過ぎない。
(3)DSM-5やICD-11のようなカテゴリー診断は非科学的である。
まずはこの3つについて解説します。
精神科は症状による診断であることを忘れてはなりません。いくつか項目があり、例えば6個当てはまればその病気と診断する方法ですが、そのうち3〜4つが当てはまるという子もいるわけです。実際、そういう子が増えていますから、発達障害といわれている子どもたちの大半は、単なる発達の凸凹にすぎません。(杉山登志郎)出典:東洋経済education × ICT編集部(2023)
たとえば、ADHDの診断基準ですと、
「課題または遊びの活動中に、しばしば注意を持続することが困難である」という診断項目があります。
これはアンケート調査のようなものですよね。
普通、病気というのは病気を引き起こす病気の「病因」があります。
コロナだったら、コロナウィルスが見つかるわけです。
でも、発達障害は症状を「調査」するだけで診断名を決めてしまいます。
この《症状のみによる診断》を「カテゴリー診断」と言います。
経験豊富とは言えない精神科医が、カテゴリー診断の症状リストに該当するかどうかだけで診断すると、どうしても過剰診断になってしまうのです。(杉山登志郎)出典:『トラウマ』(2024)
そして、診断がつくことが改善につながるのかというと、必ずしもそうではありません。
【薬】《とりあえず薬を出しましょう》という対応が本当に治療につながっているのか?
【学校】《ADHDと診断されました》という報告が学校教育の場で活かされているのか?
この二つについて解説してみます。

3.薬物治療の今
本来、医療でも経済でも、《効果のないものは使わない》という考え方が普通だと思います。
いわゆるエビデンス(科学的根拠)ですね。
科学的エビデンスを求める社会全体の流れの中で、心理療法的な治療は認知行動療法が主流となり、薬物療法について様々なエビデンスが示されるようになりました。(杉山登志郎)出典:『トラウマ』(2024)
認知行動療法というのは、一般に言いますと、その人のものの見方や考え方に働きかけて気持ちを楽にする精神療法のことです。
広い意味では、「行動的支援」とも言います。
たとえば、ADHDの子に対して、《先生の指示を復唱させる》という行動支援があります。
「先生が今言ったことをもう一度言ってごらん」などと言うわけです。
ADHDの子は、多動性があり、注意の持続が苦手な場合がありますから、たったこれだけで自分の行動が改善されることがあります。
ここで大切なのは、このやり方を子どもに会得させることです。
「先生が言ったこと」は外言ですが、それを自分の頭の中で「内言」として復唱するというスキル。
それが身につくと、セルフコントロールが向上します。
これが行動支援です。出典:「ビデンスにもとづいた発達障害支援:応用行動分析学の貢献」(2009)
こうした方法に科学的根拠があるわけです。
その一方で、薬物療法については不安材料があります。
うつ病の治療を例にとりましょう。
脳神経内科の医師・田中伸明氏は次のように述べています。
病気は、「原因→病態→症状」と考え、身体科は徹底的に原因追及し、原因治療を行う。一方、精神科は患者の訴える症状を大切にし、症状によって診断を行い、症状を取り除くことに全力を傾けていく。この精神科の手法は、症状は明らかであるが原因不明の統合失調症の診断・治療できわめて有効なアプローチであった。原因が不明であるから、原因は問わない。その結果、世界標準の精神医学的診断基準であるICD-10、DSM-5でのうつ病診断も、原因を問わない様式となっている。症状だけでうつ病と診断できる便利な基準であるが、症状に対する病名なので対処療法に陥りやすい。例えば、コロナ感染症による発熱ならば発熱病と呼ばず、原因であるコロナウィルスを特定して抗ウイルス薬で治療するだろう。出典:『ポリヴェーガル理論による「うつ病」治療革命』2024
発達障害の診断と同じですね。
うつ病の場合、科学的エビデンスは非薬物療法に移行していると言われています。
この著書では、「抗うつ薬の効果が約3割」という研究結果を紹介しています。出典:Selective publication of antidepressant trials and its influence on apparent efficacy(2008)
つまり、7割は効果がないということです。
また、抗うつ薬とプラセボ(ニセモノの薬)を飲んだ場合の比較実験の結果、プラセボ群で効果がみられた人が42%もあったという研究結果もあります。出典:「プラセボ投与時に見られる改善率」(2013)
こうした状況の中、海外のうつ病治療では、抗うつ薬の治療は制限されていて、その代わりにマインドフルネスによる「第三世代認知行動療法」、身体にアプローチする「身体心理療法」、電気や磁気やVRを利用した「神経調整療法」などが普及しているといいます。
実際、日本のうつ病治療は薬物治療が中心なのに、患者は増える一方です。
今のままでは駄目だということでしょう。
また、現在の抗うつ薬や発達障害の治療薬の多くはモノアミン仮説に基づいて作られていますが、そもそもモノアミン仮説が正しいかどうかはまだ立証されていません。
そこから考え直さなければならない時代になって来ています。

4.学校教育の今
私の現場経験で言いますと、《困難を抱えた子》→《カテゴリー診断》という流れは、小学校に就学する時や小学校に入ってから通常学級に在籍していたけど困難な場合に多くみられました。
これには、①学校制度という環境の問題と、②先生の力量という環境の問題があります。
本来、カテゴリー診断は、①②の環境を改善するために実施する意味が大きいはずです。
ADHDと診断された子の教室環境を工夫するとか、指導法を工夫するとかです。
しかし、こうした工夫をするには学校や教員に《改善する余裕》が必要です。
具体的には《お金》や《時間》です。
また、研修制度や教員免許制度などの《システム》の改善も必要です。
それが十分に出来ていない状況下で、カテゴリー診断をしても《改善につながらない》という実情があると思います。
例えば「漢字が書けない」という学習のつまずきを抱えた子どもがいるとします。この場合、短期記憶や作業記憶が弱いから書けないのか、視覚的な認知の偏りがあるのか、過敏性があってノートや教科書を見ることに抵抗があるのかなど、一人ひとり抱えている問題は異なります。(杉山登志郎)出典:東洋経済education × ICT編集部(2023)
こうした分析が出来ないままに授業をしているのが多くの実態ではないでしょうか。
学校現場に多い「年齢相応にできるのは当たり前。できないときだけ叱る」というやり方は、発達に凸凹のある子どもたちには向きません。出来事の背景を読み取る力が弱い子は、なぜ叱られているのかを理解できないのです。やみくもに叱責するのではなく、「こうすればうまくいく」という方法を丁寧に教えてあげてください。また子どもたちの「できていること」「努力していること」を確認してあげるとよいでしょう。(杉山登志郎)出典:東洋経済education × ICT編集部(2023)
「こんなことも出来ないのか?」に類した言葉は今も学校現場で聞かれるようです。
子どもの問題行動を探して、叱る・注意するのが仕事だと思っている先生もいるようです。
このような「環境」のもとでは、カテゴリー診断は意味を持ちません。
そういう実態が未だにあるということです。
特別支援教育が始まったのは2007年ですが、17年経過した今も、その目的は実現できていません。

5.「発達凸凹」に対する無理解
「発達凸凹」に対する無理解はその象徴です。
「発達凸凹」は病気や障害ではありません。
発達障害といわれている子どもたちの大半は、単なる発達の凸凹にすぎません。通常の発達と比べると凸凹があるものの、それが普遍的なハンディキャップとは言い切れないケースです。確かに得意なことと苦手なことの差が大きく凸凹がある。しかし凸凹があること自体は病気でもないし、障害でもありません。(杉山登志郎)出典:東洋経済education × ICT編集部(2023)
私が思うに、「発達凸凹」は《個性》や《性格》の範疇です。
発達の《早い・遅い》という時間差もあるでしょうし、知能検査などの項目ごとの《得意・不得意》もあるでしょう。
それらを含めて「発達凸凹」だと考えます。
そして、「発達凸凹」は発達します。
さまざまな問題行動が発達の凸凹によって起こっている場合は、脳の機能が発達する小学校4年生になると、しだいに和らぎ落ち着いてきます。(杉山登志郎)出典:東洋経済education × ICT編集部(2023)
私の現場経験からも、低学年で心配されていたお子さんが、女子は4年生、男子は5年生くらいで変化します。
ですから、それまでに《見守ること》も大切です。
ただし、この《見守る》が実現できない場合が少なくありません。
見守らないで放置してしまうケースが多いのです。
放置するとどうなるかというと、凸凹がありますから、親や教師から叱責を受けたり、友達からいじめられたり、集団行動が苦手なのでしょっちゅう問題行動を起こしたりして叱られます。
こては、凸凹への支援が足りずにそうなる場合と、凸凹への理解が足りずに強い指導をしてしまう場合の2パターン(事前支援不足と不適切な事後指導)です。
これは《見守ること》が出来ていないということです。
そうなると発達凸凹児は、《叱られることに対する緊張》や《叱られてばかりいる罪悪感》や《叱られることによる無力感》を感じてしまい、高学年での発達の可能性を失うことになります。
これが「発達凸凹」に対する無理解(不適切な対応)です。

6.まとめ
どうでしょうか。
ここまで読んでいただいて(1)~(3)の《考え方》が理解できましたでしょうか。
(1)発達障害の大半は、病気でもないし、障害でもない。
(2)小児科医や児童精神科医を受診する児童の9割以上が発達凸凹に過ぎない。
(3)DSM-5やICD-11のようなカテゴリー診断は非科学的である。
次回は(4)から解説したいと思います。






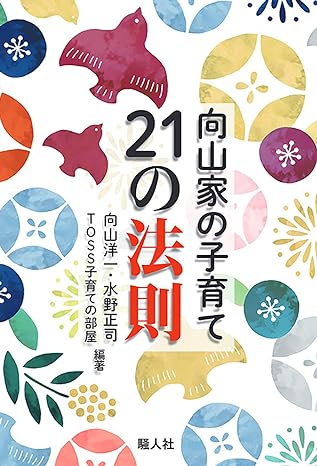
発達障害という言い方はストレートだから、オブラートに包むために発達の凸凹と表現をするケースが見られるように思います。どんな凸凹なのか、社会参画におけるどんな支障があるのか、どんな手立てがあるか(例えば、視力が弱いので、コンタクトレンズや眼鏡をかければ支障ない等)一人一人よく見ていきたいです。
「言い方」という視点は重要ですね。
そして、問題の本質は、その人が使っている「その言葉」はどんな定義なのかということですよね。
本当の意味での「発達障害」なのか?
世間話程度の「発達障害」なのか?
本当の意味での「発達凸凹」なのか?
なんとなく使っているのか?
教員でもバラバラですよね。涙
見守るというのは、いつも気にかけているということでいいのでしょうか?例えば、何気なく声をかける、一緒に遊ぶ、など。また、必要を感じた時には介入するのが良いのでしょうか。私は臨職なので、直接的な介入はせず、気になったことがあれば、常勤に伝えるなどで良いのでしょうか。
TSプロトコール(「パタパタ体操」)をやってみてください。